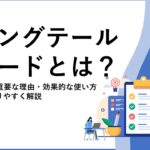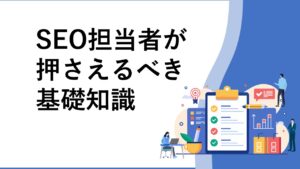SEO
WEB TANOMOOO
【無料ツールで実践】キーワードプランナーを使ったSEO戦略の立て方【初心者向け】
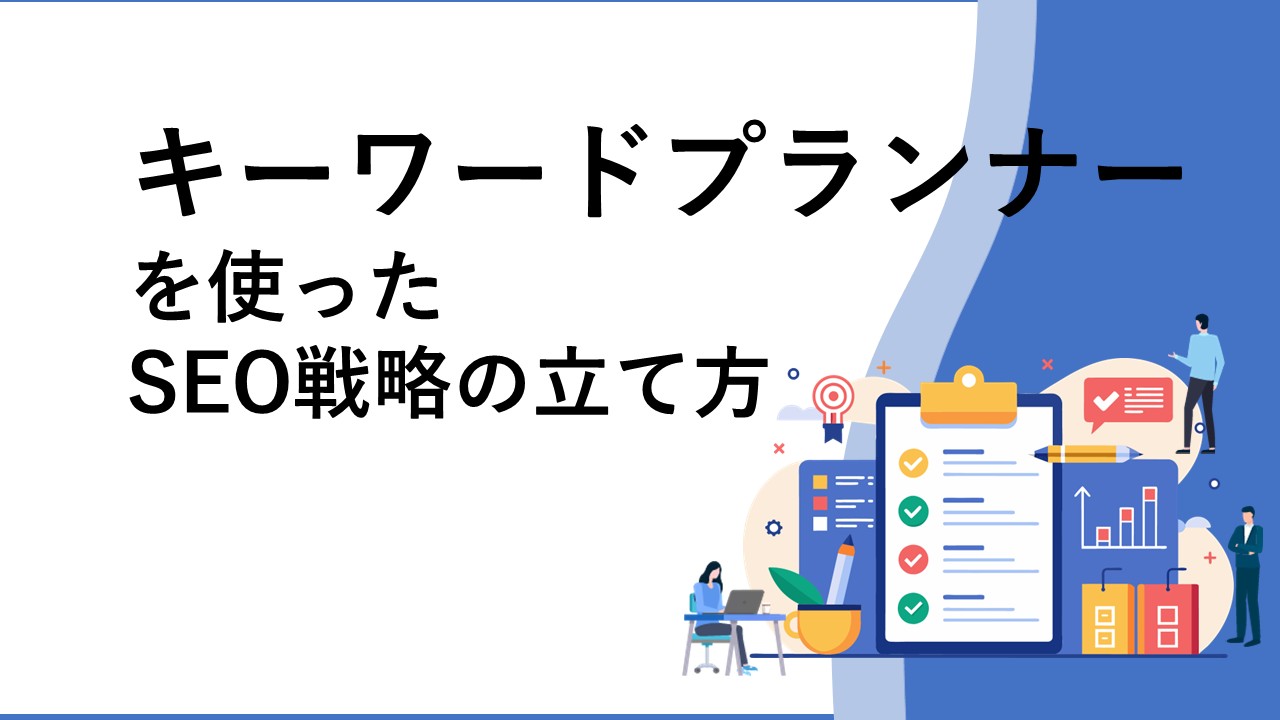
キーワードプランナーとは?初心者が押さえるべき基本情報
キーワードプランナーとは?
新たなキーワードの発見や、既存キーワードの検索ボリューム・競合状況を調べることができ、SEOやGoogle広告の戦略立案に役立ちます。
特に、適切なキーワードを選定することは、ターゲットとなるユーザーに効果的にアプローチするうえで欠かせません。
例えば新商品を訴求する際に、ユーザーが検索する語句を事前に把握しておくことで、的確なコンテンツ制作や広告運用が可能になります。
操作は初心者にも分かりやすく設計されており、基本的なキーワード戦略を立てたい方にとっても有効なツールです。
Googleキーワードプランナーの基本概要
新しいキーワードの候補や、検索ボリューム、予測データを手軽に取得できます。
操作は直感的で、キーワードを入力するだけで、関連語や類義語を含むリストが自動的に表示されます。
地域、言語、デバイス別にデータを絞り込む機能もあり、ターゲットごとの詳細分析が可能です。
また、Google広告との連携により、検索広告とSEOの戦略を一体的に設計できる点も大きな強みです
精度の高い公式データが取得できるため、信頼性の高いキーワードリサーチが行えます。
無料で利用できるツールの特徴
Googleキーワードプランナーの無料版は、初心者にとって非常に有用なキーワード調査ツールです。
無料でも基本的な機能を利用でき、SEO戦略の初期段階で重要なデータを収集することが可能です。
ただし、無料版にはいくつかの制限があります。たとえば、検索ボリュームは「100〜1,000」などの幅で表示され、正確な数値は提供されません。
また、クリック単価(CPC)や競合性に関する詳細データも一部非表示になります。これらの制限は、有料広告出稿を行っていないアカウントに対して適用されます。
無料版で利用できる主な機能は以下のとおりです。
・新しいキーワードの発見
・検索ボリュームの範囲表示
・基本的なフィルタリング(地域、言語、期間など)
・競合性の確認(ざっくりとした傾向)
一方で、以下のような制限があります。
・検索ボリュームの正確な数値が確認できない
・一日の検索クエリ回数に制限がある
・クリック単価やコンバージョン見込みなどの予測データが非表示
無料版を最大限に活用するためには、次のような工夫が効果的です。
・異なるワードや表現を繰り返し検索することで、より多角的なキーワード候補を抽出する
・ラッコキーワードなどの外部サジェストツールを併用し、検索ニーズを網羅的に把握する
・定期的にデータを確認し、戦略をアップデートすることで、トレンドの変化に柔軟に対応する
こうした工夫を取り入れることで、無料版であっても実用的なキーワードリサーチが可能になります。
Google広告アカウントの登録が必要な理由
Googleキーワードプランナーを最大限に活用するには、Google広告アカウントの登録が必須です。
アカウントを作成することで、キーワードの検索ボリュームや競合性、広告費用の予測といった詳細なデータにアクセスできるようになります。
特に、正確な検索ボリュームの数値やクリック単価(CPC)、コンバージョンの予測値などは、アカウントを保有している場合にのみ表示される情報です。
登録手続き自体はシンプルで、Googleアカウントを持っていればすぐに開始できます。
必要な情報は、メールアドレスやビジネス名、国や通貨などの基本的なビジネス情報、そして支払い方法の設定です。
広告の配信をすぐに始めなくても、アカウント作成だけでキーワードプランナーの機能は利用可能になります。
また、Google広告アカウントを活用すれば、SEOだけでなく広告運用における分析精度も大きく向上します。
検索ボリュームや競合性を定期的に確認しながら、広告キャンペーンの設計や効果測定にも役立てることができます。リアルタイムでデータを取得し、変化に応じた迅速な戦略調整が行える点も、アカウント登録による大きなメリットの一つです。

キーワードプランナーの主要機能と活用法
キーワードプランナーには、SEOや広告戦略を立てる上で有用な複数の機能が搭載されています。
代表的なものとして、「新しいキーワードを見つける」機能と、「検索ボリュームと予測のデータを確認する」機能があり、それぞれ異なる用途で活用されています。
これらの機能を使いこなすことで、ターゲットに適したキーワードを効率よく選定できるだけでなく、検索需要の傾向や将来的な広告費用の見通しまで視野に入れた戦略を構築することが可能です。
特に初心者の方にとっては、まず基本的な2機能を理解し、SEOや広告にどのように活かせるかを学ぶことが、ツール活用の第一歩になります。
以下のセクションでは、各機能の具体的な使い方と、それがどのようにSEO戦略や広告設計に役立つのかを詳しく解説していきます。
「新しいキーワードを見つける」機能の活用方法
「新しいキーワードを見つける」機能は、キーワードプランナーの中でも最も基本的かつ重要な機能の一つです。
入力した語句に関連する新しいキーワード候補を自動的に提案してくれるため、まだ競合が少なく、成果につながりやすいキーワードを発見するのに役立ちます。
たとえば、「デジタルマーケティング」と入力すると、「SEO対策」や「コンテンツマーケティング」など、関連する幅広い語句が一覧で表示されます。
こうした候補の中から、自社の商品やサービスに合致する語句を選び、戦略に組み込むことで、ニッチ市場やトレンドに対応した効果的なSEO対策が可能になります。
キーワードの選定にあたっては、単に表示された語句を並べるだけでなく、検索ボリュームや競合性を併せて確認し、自社のリソースに応じた難易度のキーワードを選ぶことが重要です。
さらに、発見したキーワードをページタイトル、見出し、本文などに自然な形で取り入れることで、検索エンジンからの評価も高まり、上位表示につながります。
この機能を習慣的に活用し、常に新しい検索トレンドに目を向けることが、継続的なSEO強化のカギとなります。
「検索ボリュームと予測のデータを確認する」機能の使い方
「検索ボリュームと予測のデータを確認する」機能は、特定のキーワードがどの程度検索されているか、また将来的にどれほどの検索需要が見込めるかを分析するために活用されます。
この機能を利用することで、コンテンツの企画や広告出稿の優先順位を、より正確に判断することができます。
検索ボリュームとは、一定期間内に特定のキーワードが検索された回数の平均値を示すもので、ユーザーの関心度を測る指標として非常に重要です。
検索ボリュームが高いキーワードは、多くのトラフィックを集める可能性がある一方で、競合も多くなる傾向があります。
逆に検索数が少ないキーワードでも、特定のニーズにマッチすれば高い成果が見込めることもあります。
予測データでは、過去の検索トレンドや季節要因に基づいて、将来的な検索回数やクリック数、表示回数などが算出されます。
これにより、今後検索需要が高まりそうなキーワードを先回りしてコンテンツに反映させるといった、戦略的なアプローチが可能になります。
これらのデータを活用する際には、単なる数値としてではなく、ユーザーの検索意図や市場の動きを読み取る材料として解釈することが重要です。
特に予測値はあくまでシミュレーションであるため、常に最新データと照らし合わせて柔軟に調整を行う姿勢が求められます。
キーワード候補のフィルタリングとカテゴリ分け
キーワードプランナーで表示されるキーワード候補は非常に多く、そのままでは情報が多すぎて活用しきれないことがあります。そのため、効果的なSEO戦略を立てるには、候補の中から目的に合ったキーワードを絞り込む「フィルタリング」と、分類して整理する「カテゴリ分け」の作業が不可欠です。
まずフィルタリングでは、次のような基準をもとにキーワードを取捨選択します。
・検索ボリューム:多くの検索がされているキーワードは集客効果が高い一方、競争も激しいためバランスを見極める必要があります。
・競合性:競争が激しいキーワードばかりを狙うと上位表示が難しくなるため、競合が少ないニッチなキーワードも積極的に検討します。
・関連性:自社のサービスやターゲットユーザーに関連性が高いキーワードを優先することで、コンバージョン率の高い訪問者を呼び込めます。
次にカテゴリ分けでは、抽出したキーワードを以下のような観点でグループ化します。
・テーマ別の分類:たとえば「商品名」「お悩み解決」「レビュー」「比較」など、コンテンツの切り口に応じた分類。
・ユーザーの検索意図別:「情報収集」「比較検討」「購入直前」など、検索フェーズに応じた分類。
・施策上の優先度:ビジネスインパクトや実装のしやすさをもとに、すぐに着手すべきキーワード群と中長期的なターゲットを分けて整理します。
このようにフィルタリングとカテゴリ分けを組み合わせることで、キーワードの選定がより戦略的かつ効率的になります。整理されたキーワードリストは、コンテンツ制作や広告設定にすぐに活用できる貴重な資産となり、SEO施策全体の精度を高める基盤になります。
SEO戦略におけるキーワード選定の重要性
SEOにおける成果は、キーワード選定の質に大きく左右されます。
ユーザーが実際に検索する語句を的確に把握し、それに基づいたコンテンツを提供することで、検索結果での上位表示が可能となり、ターゲット層からのアクセスを効率的に獲得できます。
適切なキーワードを選ぶことは、検索エンジン対策だけでなく、ユーザーとの接点をつくる上でも重要です。検索ニーズに合ったコンテンツは、訪問者の関心を引きやすく、ページの滞在時間やコンバージョン率の向上にも寄与します。
キーワード選定では、以下の視点をバランスよく取り入れることが求められます。
・ユーザーの検索意図の把握:情報収集段階か購入検討段階かを見極め、適切な語句を選びます。
・検索ボリュームと競合性の評価:アクセス数を見込める一方で、競合が多すぎるキーワードはリスクも高いため、適度なバランスが重要です。
・ロングテールキーワードの活用:検索数は少なくても、具体的なニーズにマッチする語句を狙うことで、質の高い訪問者を集められます。
・継続的な見直しと改善:一度決めたキーワードを固定せず、成果や市場動向に応じて戦略を柔軟に見直すことも不可欠です。
こうした観点を踏まえてキーワードを選定することで、単なるアクセス増加にとどまらず、成果につながる質の高いSEO施策を実現することができます。
月間平均検索ボリュームの分類(スモール・ミドル・ビッグキーワード)
キーワードを選定する際には、月間平均検索ボリュームに基づいて分類することで、SEO戦略の立案がより明確になります。一般的に検索ボリュームは、スモール・ミドル・ビッグの3つに大別され、それぞれ特性と狙いどころが異なります。
スモールキーワードは、月間検索回数が100回未満のキーワードを指し、ニッチな市場や特定の課題に対する解決策を求めるユーザーに向いています。競合が少なく、上位表示を狙いやすいため、初心者でも成果を出しやすいジャンルといえるでしょう。また、購入意欲の高い検索が含まれることも多く、コンバージョン率の高いトラフィックが期待できます。
ミドルキーワードは、月間100〜1,000回程度の検索ボリュームを持つ中規模のキーワードです。トピックの幅が広く、情報収集から比較検討段階のユーザーを含むため、幅広いコンテンツ展開に適しています。一定の競合はあるものの、工夫次第で上位表示が可能であり、安定したアクセスを集めるのに効果的です。
ビッグキーワードは、月間1万回以上の検索ボリュームを持つ人気キーワードで、ブランド認知や大規模な集客を狙う際に活用されます。ただし、競合が非常に激しいため、上位表示には高品質なコンテンツとドメインパワーが必要になります。また、コンバージョン率は比較的低くなる傾向があるため、単独で狙うのではなく、ロングテールキーワードと組み合わせて戦略的に運用することが効果的です。
このように、検索ボリュームに応じたキーワードの特性を理解し、それぞれの強みを活かしたバランスの取れた構成を意識することで、SEO施策の幅を広げることができます。
関連キーワードの収集と選定方法
SEOの効果を最大化するには、メインキーワードだけでなく、関連キーワードの収集と選定が欠かせません。
関連キーワードは、ユーザーの検索意図の広がりに対応し、より多角的なコンテンツ構成や流入経路の確保に貢献します。
まず、関連キーワードを効率的に収集するには、Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどの専用ツールを活用することが有効です。
こうしたツールでは、入力した語句に基づきユーザーの検索傾向を反映した候補が一覧で表示されます。
また、競合サイトのコンテンツや検索結果のサジェスト欄、Q&Aサイトの投稿なども、ユーザーが実際に使用している言葉を探るうえで貴重な情報源となります。
収集したキーワードは、いくつかの基準に沿って選定・整理していく必要があります。
特に重視すべきは、検索ボリュームと競合性、そして自社の提供価値との関連性です。検索数が一定以上ありながら、競合が強すぎないキーワードは特に狙い目です。
また、ユーザーの検索フェーズ(情報収集、比較、購入検討など)に応じたキーワードを優先的に選定することで、より意図に即したコンテンツが作成できます。
選定した関連キーワードは、見出しや本文、メタディスクリプションなどに自然な形で組み込むことで、検索エンジンへの適切な評価とユーザーの理解促進につながります。
さらに、内部リンク戦略や関連記事への誘導にも応用することで、サイト全体の回遊性とSEO効果を高めることが可能です。

キーワードプランナーを使った調査手順と分析設定
キーワードプランナーを効果的に活用するには、ツールの基本的な操作手順と分析の設定方法を理解しておくことが重要です。
調査の流れを明確にしておくことで、効率的に必要なデータを収集でき、SEO戦略や広告運用に活かすことができます。
調査は主に、
①検索キーワードの入力
②関連キーワードの抽出
③データの絞り込み
④デバイスや地域の設定
⑤キーワードの評価と整理
といった手順で進められます。これらのプロセスを一貫して実行することで、ターゲットユーザーのニーズや市場の傾向を多角的に把握できます。
また、分析の際には、地域・言語・期間・デバイスなどの条件設定が非常に重要です。ターゲットエリアや検索タイミング、利用端末に応じたデータに絞り込むことで、より現実的で実践的な戦略を立てることが可能になります。
特に、スマートフォン利用者が多い市場では、モバイルデバイスでの検索傾向を重視した分析が欠かせません。
このセクションでは、こうした各手順を順に解説し、実際にキーワードプランナーを用いて調査を行う際の注意点や活用のコツについても取り上げていきます。
検索キーワードの入力と関連キーワードの表示
キーワードプランナーの調査は、まず「検索キーワードの入力」から始まります。
ここでは、ビジネスやサービスに関連する語句や、ユーザーが検索しそうなワードを入力し、そこから派生する関連キーワードを洗い出していきます。
具体的なフレーズを入力することで、より実践的で関連性の高いキーワードを取得しやすくなります。
たとえば「Web広告」と入力すると、「リスティング広告」「ディスプレイ広告」「Web広告 費用」などの派生語句が表示されます。
こうした関連キーワードは、ユーザーの検索意図や市場の興味関心を反映しているため、SEOや広告配信の土台として非常に有効です。
このプロセスでは、以下のような工夫が効果的です。
・具体性を意識して入力する:抽象的なワードよりも、サービス名や地域名を含めると精度が上がります。
・複数パターンを入力して比較する:類義語や言い換え表現を試すことで、幅広い検索傾向を把握できます。
・ユーザーの立場で検索語を考える:企業視点ではなく、実際に検索するユーザーが使いそうな表現を意識することが重要です。
抽出されたキーワードは、検索ボリュームや競合性とあわせて表示されるため、質と量の両面から候補を評価できます。特に初心者は、このステップで得られる関連語の広がりを活用し、自社に合った語句を見極める訓練を重ねることが成果に直結します。
地域・言語・期間の設定による絞り込み
キーワードプランナーでより精度の高い分析を行うには、地域・言語・期間といった条件設定による絞り込みが不可欠です。
これらの設定によって、ターゲットユーザーの検索行動により近い形でデータを取得でき、無駄のないキーワード選定が可能になります。
まず地域設定では、広告やSEOの対象とする商圏に合わせて、国単位はもちろん、都道府県・市区町村レベルまで細かく指定することができます。たとえば「名古屋市」でWeb広告を出す企業であれば、名古屋市内の検索傾向に絞ってデータを見ることで、ローカルニーズに合ったキーワードを抽出できます。
言語設定では、対象ユーザーが使用する言語(日本語、英語など)を選ぶことが可能です。特に多言語対応サイトやインバウンド施策では、日本語以外の検索傾向も重要な判断材料になります。
期間設定では、直近の30日間、過去12か月などのスパンを指定して、時期ごとの検索動向を確認できます。季節変動がある商品やイベント系のキーワードでは、この期間設定がとくに有効です。たとえば「クリスマスケーキ」などの季節キーワードは、10月〜12月にかけて検索数が急増する傾向が見られます。
これらの絞り込みを組み合わせることで、よりリアルで実用的なキーワードデータを得ることができ、無駄な広告費やSEOリソースの削減にもつながります。
表示結果からのキーワード評価とCSV出力
キーワードプランナーでは、検索キーワードの入力後に表示される関連語の一覧から、各キーワードの評価を行い、必要に応じてCSV形式で出力することが可能です。
この機能を活用することで、戦略的に価値のあるキーワードを効率よく管理・分析できます。
表示されたキーワードには、検索ボリューム、競合性、入札単価(上限と下限)などのデータが含まれており、これらの指標をもとに評価を行います。
たとえば、検索ボリュームが一定以上ありながら競合性が低いキーワードは、SEOでも広告でも狙い目といえます。
一方で、競合が高すぎるキーワードは、上位表示やクリック単価の観点からリスクが伴うため、戦略的な判断が必要です。
評価の際には、次のような視点が有効です。
・検索ボリュームと競合性のバランス
・自社サービスとの関連性の高さ
・想定されるユーザーの検索意図
・過去の実績との照合(広告配信履歴など)
必要なキーワードがある程度まとまったら、CSVで出力しておくと、後のコンテンツ制作や広告設計に役立ちます。出力したファイルは、ExcelやGoogleスプレッドシートで加工しやすく、優先順位付けやカテゴリ分けを効率的に進めることができます。また、チーム内での共有や、レポート資料としての活用にも適しています。
このように、キーワードプランナーの評価機能と出力機能を組み合わせることで、調査結果を資産として活用できる体制を整えることが可能になります。
SEO戦略におけるキーワードの役割と活用方法
SEO対策においてキーワードは、検索エンジンとユーザーをつなぐ“接点”となる重要な要素です。
適切に選定されたキーワードは、コンテンツの方向性を定め、上位表示を狙ううえでの軸になります。
また、検索結果からの流入を高めるだけでなく、ユーザーのニーズに合致した情報を提供するための指針としても機能します。
SEOにおけるキーワードの活用は、単に記事に多くのキーワードを詰め込むことではありません。むしろ、検索意図に即した文脈の中で自然にキーワードを使い、ページのテーマや構成と整合性を持たせることが求められます。
具体的には、ページタイトルや見出し(H2・H3)、本文の冒頭や結びの部分など、ユーザーの注目が集まりやすい箇所に適切に配置することで効果が高まります。
また、検索意図に合わせたキーワードのグルーピングも重要です。
「調べたい」「比較したい」「購入したい」といったフェーズごとに異なるキーワードを使い分けることで、ユーザーの段階に応じたコンテンツ設計が可能になります。
たとえば、「Web広告とは」というキーワードは初心者向けの導入コンテンツに適しており、「Web広告 費用 相場」であれば検討フェーズのユーザー向けに有効です。
さらに、キーワード選定はコンテンツ制作だけでなく、内部リンク設計やサイト構造の整理にも役立ちます。
キーワードの関係性を意識して記事同士をつなぐことで、検索エンジンからの評価が高まり、回遊率や滞在時間の向上にもつながります。
検索意図に合わせたキーワード設計の考え方
SEO戦略で成果を上げるためには、単に検索ボリュームの多いキーワードを選ぶだけでなく、ユーザーの検索意図(インテント)を正確に把握し、それに応じたキーワード設計を行うことが重要です。
検索意図とは、ユーザーが検索エンジンに入力する言葉の裏にある「知りたいこと」「やりたいこと」「解決したい課題」のことです。
検索意図は大きく分けて、以下の3つに分類されます。
・情報収集型(Know):「Web広告とは」「SEOの仕組み」など、知識を得るための検索
・比較検討型(Do):「Web広告 比較」「リスティング広告 メリット」など、行動の意思を伴う検索
・購入・申し込み型(Buy):「Web広告 依頼」「Web広告 料金プラン」など、具体的なアクションを前提とした検索
たとえば、集客を目的としたLPでは「申し込み意図」が強いキーワードを優先し、ブログ記事では「情報収集意図」に沿ったキーワードを中心に設計するのが効果的です。このように検索意図を分類し、それに沿ってキーワードを配置・活用することで、コンテンツの目的とユーザーのニーズを一致させることができます。
また、検索意図は時間とともに変化する場合があるため、アクセス解析やサーチコンソールなどのデータを活用し、定期的に見直すことも重要です。
コンテンツへの自然な組み込みと配置の工夫
効果的なSEO対策では、キーワードをただ文章中に散りばめるのではなく、読者にとって自然な形で組み込むことが重要です。不自然にキーワードを繰り返すと、読みづらさを招くだけでなく、検索エンジンからスパムと判断されるリスクもあります。
キーワードの配置場所として意識すべきポイントは以下の通りです。
・タイトル(titleタグ)やH1見出し:ページのテーマを示す場所であり、最も重要なキーワードを含めるべきです。
・H2・H3見出し:文章の構成を示す要素であり、検索意図と整合性を持ったキーワードを使用することで、検索エンジンと読者の双方に伝わりやすくなります。
・本文の冒頭・中盤・結論部:文章の節目にキーワードを自然に入れることで、読みやすさを損なわずにSEO効果を高められます。
・メタディスクリプションやalt属性:検索結果での表示や画像の説明にも関わるため、適切なキーワード活用が求められます。
このような配置を意識しつつ、文脈の中で無理のない形でキーワードを活用することが、SEOとユーザー体験の両立につながります。また、同じキーワードを繰り返すのではなく、関連語や言い換え表現を適度に織り交ぜることで、自然な文章構成と検索エンジンの幅広い評価が得られます。
競合サイトのキーワード活用事例を参考にする
効果的なキーワード戦略を立てるためには、自社の視点だけでなく、競合サイトのキーワード活用事例を参考にすることも重要です。
競合他社がどのようなキーワードで検索上位を獲得しているかを分析することで、見落としていた需要や新たな切り口を発見できます。
まず、競合サイトの調査では、SEO分析ツール(例:Ubersuggest、Ahrefs、SE Rankingなど)を使って、ドメイン単位での流入キーワードやランディングページの傾向を把握します。
たとえば、同じ業種で上位表示されているサイトが「地域名+サービス名」「費用+目的」などの複合キーワードで流入を得ている場合、自社サイトでも類似の切り口を検討する余地があります。
さらに、検索結果ページ(SERPs)を実際に観察し、競合がどのようなタイトルやディスクリプションでクリック率を高めているかを確認することも有効です。
自社が狙いたいキーワードで上位表示されているページをいくつかピックアップし、構成や見出し、使用されている言い回しなどを丁寧に分析しましょう。
ただし、あくまで「参考」として活用することが大切です。競合の真似をするだけでは差別化につながらないため、発見したキーワードを自社の強みや提供価値に紐づけて再構築し、独自性のあるコンテンツに落とし込む視点が求められます。
キーワード選定はSEOの起点
SEO施策の第一歩は、ターゲットユーザーがどのようなキーワードで情報を探しているかを理解することです。
キーワード選定は、単なる言葉選びではなく、ユーザーのニーズや検索意図に応えるための戦略的な設計プロセスです。
適切なキーワードを選ぶことで、検索エンジンからの評価を高め、見込み客の流入を効率よく促進できます。
この記事で紹介したように、Googleキーワードプランナーなどのツールを活用し、検索ボリューム・競合性・関連性を踏まえたうえでキーワードを評価・分類し、検索意図に即したコンテンツへと落とし込むことがポイントです。また、定期的な見直しと競合分析を通じて、柔軟かつ継続的な改善が求められます。
キーワード選定は、SEO全体の成果を左右する「起点」であると同時に、コンテンツ制作、内部リンク設計、さらにはCV(コンバージョン)獲得に至るまで、あらゆるマーケティング施策の土台となる重要なプロセスです。手間を惜しまず丁寧に取り組むことで、長期的に安定した集客と成果につながるでしょう。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。