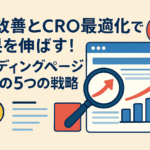LP.HP関連
WEB TANOMOOO
設計で8割が決まる!コンバージョンに強いランディングページの構築思考とは

設計の質がCVを決める!成果直結のLP戦略を始めるために知っておきたいこと
LPとホームページの違いを理解する
ランディングページ(LP)とホームページ(Webサイトのトップページや企業サイト)は、役割も構成も大きく異なります。
ホームページは企業全体の情報を網羅的に発信し、さまざまなユーザーの訪問を想定した設計です。一方、LPは「特定のターゲットに、ひとつの行動を促す」ことを目的に作られており、情報は最小限に絞り込まれています。
また、ホームページにはナビゲーションメニューや複数のリンクがあり、回遊性を高める構造ですが、LPは訪問者にひとつの流れで読み進めてもらうため、基本的に1ページ完結型で、リンクも最小限です。
この違いを理解していないと、成果の出にくいLPになってしまう可能性があります。目的に応じて設計を使い分けることが、Web施策の成功には不可欠です。
LP設計の基本構成要素
成果につながるランディングページ(LP)を設計するには、ただ情報を並べるだけでは不十分です。ユーザーの心理や行動を意識した「構成の設計」が不可欠です。以下は、コンバージョンを獲得するための基本的な構成要素です。
ファーストビュー(第一印象)
ページを開いた瞬間に伝えるキャッチコピーやビジュアル。ここで「自分に関係がある情報だ」と感じてもらえるかが勝負です。
共感パート(課題提示)
ユーザーの悩みやニーズに寄り添い、「わかってくれている」と思わせることで、離脱を防ぎます。
解決策の提示
サービスや商品がどのように課題を解決するかを明確に説明します。具体例や実績があると信頼性が高まります。
メリット・差別化ポイント
他社との違いや、自社ならではの強みを打ち出すことで、選ばれる理由を強化します。
お客様の声・事例紹介
第三者の声は信頼獲得に有効です。特に類似属性の顧客事例があると説得力が増します。
CTA(行動喚起)
最終的にとってもらいたい行動(例:問い合わせ、資料請求)への導線を、分かりやすく、心理的ハードルの低い形で設置します。
これらの構成はあくまで基本形ですが、業種やターゲットによって最適な順序や要素は変わります。設計段階でしっかりと「誰に、何を伝え、どう動いてもらうか」を見据えることが、成果の出るLP制作の第一歩です。
成果につながるLP設計のポイントと実践アプローチ
ただ構成をなぞるのではなく、「ユーザーがなぜ動くのか?」という視点から設計全体を見直すことで、CV(コンバージョン)率を大きく左右するLPに仕上げることができます。
ユーザー視点で考える導線設計のコツ
LPの成否を分ける最大のポイントのひとつが「導線設計」です。
ユーザーが自然な流れでスクロールし、最終的に行動を起こすまでの一連の流れを、ストレスなく設計することが求められます。
導線設計において重要なのは、「誰が、どんな状態でこのページを訪れるか」を想定することです。
検索から来たのか、広告を経由したのか、あるいはSNSで流れてきたのか──それぞれの導入経路によって、ユーザーの情報欲求や態度変容の段階は異なります。
そのため、構成要素の順序や訴求内容は一律ではなく、「最初に信頼性を示す」「FAQを先に配置する」「CTAを中腹にも置く」など、状況に応じた柔軟な設計が効果を左右します。
ユーザーの思考や感情の変化に沿った導線を意識することで、CVへの抵抗感を減らし、スムーズな行動へとつなげることができます。
信頼性を高める要素の配置と見せ方
LPでコンバージョンを得るためには、「この会社・サービスは信頼できる」と思ってもらうことが不可欠です。特にWeb上では対面の安心感がないため、視覚的・論理的に信頼性を伝える設計が求められます。
信頼を醸成するための代表的な要素としては、以下のようなものがあります。
・第三者の評価(例:メディア掲載実績、ランキング受賞)
・お客様の声や導入事例
・実績データ(例:「導入社数3,000件突破」など)
・認証マークやセキュリティ対策の明示
・運営企業の情報や所在地
これらの情報を、ただ羅列するのではなく、「ユーザーが不安に感じるタイミング」に適切に配置することが重要です。たとえば、料金提示の直前やCTAのすぐ上に「お客様の声」があるだけで、安心感が大きく異なります。
視覚的にも「信頼できる印象」を与えるために、デザイン面でも過剰な装飾を避け、整ったレイアウト・統一感のあるフォント・適切な余白を意識しましょう。
CVに導くCTA設計のポイント
コンバージョン(CV)に直結する最終ステップが、CTA(Call To Action:行動喚起)の設計です。ここでユーザーが「問い合わせる」「資料請求する」「予約する」などのアクションを起こすかどうかで、LPの成果が決まります。
成果につながるCTAの設計には、以下のポイントを押さえる必要があります。
行動を迷わせないシンプルな文言
「今すぐ無料で相談する」「資料をダウンロードする」など、具体的で一歩踏み出しやすい言葉を使用します。
ユーザー心理を考慮した配置タイミング
ページの最下部だけでなく、スクロールの途中に複数設置することで、タイミングを逃さず行動を促せます。
不安の払拭と安心感の提示
「費用は一切かかりません」「いつでもキャンセル可能」など、心理的ハードルを下げる一言を添えるとCV率が高まります。
視覚的に目立たせる工夫
ボタンの色、サイズ、周囲の余白などを調整し、「どこを押せばいいか」が一目で分かるようにします。
CTAは、単に「申し込みボタンを置く」ものではなく、ユーザーの感情と行動を丁寧に設計する要の要素です。たとえ内容が良くても、CTA設計が弱ければ成果は出ません。全体設計の中で最も慎重に設計すべきパートのひとつといえるでしょう。

LP改善のPDCAとA/Bテスト活用法
むしろ公開後の改善プロセスこそが、CV率を引き上げる鍵となります。
ここでは「PDCAサイクル」と「A/Bテスト」の基本的な活用法を解説し、どのようにLP改善を継続的に進めていくべきかを紹介します。
PDCAによる継続的改善
ランディングページの効果を最大化するには、設計後の改善サイクルが欠かせません。
その中心にあるのが「PDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)」です。単にLPを公開するだけでは、ターゲットの反応や課題を見落としたままになってしまいます。
Plan(計画)
ターゲットや目的に応じて、どの要素を改善するかを仮説として立てます。たとえば「ファーストビューで離脱が多いならキャッチコピーを見直す」といった具体的な改善項目を設定します。
Do(実行)
仮説に基づき実際に修正を行い、公開します。修正は一度に多くの箇所を変えるのではなく、検証可能な範囲で行うのがポイントです。
Check(評価)
修正前後の数値(CV率、滞在時間、スクロール率など)を比較し、効果を検証します。Looker StudioやGoogleアナリティクスのレポート機能が活用されます。
Act(改善)
効果が確認できれば内容を定着させ、思わしくない場合は新たな仮説を立てて再チャレンジします。この繰り返しがLPの精度を高めていきます。
PDCAは一回で完結するものではなく、継続的に取り組むことで初めて意味を持ちます。効果が出ないLPも、試行錯誤の中で着実に改善する余地があるのです。
成果を伸ばすA/Bテスト設計
LP改善において、仮説を数値で検証する最も実践的な手法がA/Bテストです。A/Bテストとは、異なる2パターンの要素(例:キャッチコピーやCTAボタンの文言)を同時に公開し、どちらがより高い成果を出すかを比較する方法です。
テストの対象例:
・キャッチコピーの訴求軸(メリット重視 vs ベネフィット重視)
・ファーストビューの画像(人物写真 vs 商品画像)
・CTAボタンの色や文言
・フォームの項目数や配置順
A/Bテストを成功させるポイントは、「1回に1要素だけ変更する」ことです。複数の変更を同時に行うと、どの要素が効果に影響したのかが分からなくなってしまいます。
また、一定期間のテスト運用と統計的に有意なデータ数の確保も重要です。数日〜数週間の計測期間を設け、急いで判断しないよう注意しましょう。
テストの結果が思わしくない場合でも、「なぜ成果が出なかったか」を分析することで、次の仮説へとつながります。
A/Bテストは、成功の近道であると同時に、失敗から学ぶための設計支援ツールでもあります。

成果を最大化するLP設計の実行ステップ
目的整理とペルソナ設定
成果を上げるLPは、制作前の「設計」で方向性の8割が決まると言っても過言ではありません。その第一歩が、「誰に・何を・なぜ伝えるのか」という目的の明確化と、ペルソナ(理想的な顧客像)の設定です。
目的整理のポイント
・LPで達成したい成果(例:資料請求数の増加、来店予約の獲得)を明確にする
・ユーザーの行動目標(例:ボタンを押す、フォームを送信する)を一つに絞る
・サイト全体ではなく、LP単体で完結させることを意識する
ペルソナ設定の観点
・年齢・性別・職業・ライフスタイル
・現在抱えている悩みや不安
・情報収集の手段(SNS、検索、口コミなど)
・競合他社と比較したときに求める決め手
目的とペルソナが曖昧なままLP制作を始めると、メッセージがぼやけてCV率も下がりがちです。逆に、ペルソナの心理や生活背景まで深掘りしておけば、コピーや構成すべてに一貫性が生まれ、刺さるページ設計が可能になります。
ワイヤーフレームと構成案の作成
目的とペルソナが固まったら、次は「構成」と「見せ方」の設計に入ります。ここで重要になるのが、ページ全体の流れを可視化する「ワイヤーフレーム」の作成です。
思いつきでデザインを進めるのではなく、ユーザーの行動心理に沿った情報設計を行うことが成功の鍵です。
構成案で押さえるべき要素:
・ファーストビュー(FV):キャッチコピー+安心材料(実績・導入数など)で興味を引く
・課題提起と共感:ユーザーの悩みに共感し、「自分ごと化」させる
・サービスの魅力提示:強み・他社との違い・ベネフィットを明確に伝える
・お客様の声・実績:信頼を得るための第三者視点
・行動喚起(CTA):不安を払拭しながら、行動を後押しする
ワイヤーフレームは、構成案を「レイアウトレベル」で視覚化する作業です。文字サイズ、画像の位置、ボタンの強調なども意識して設計しましょう。
設計段階でしっかりと考え抜かれた構成は、後工程のデザインやライティングの精度にも直結します。
制作〜公開時の注意点と体制づくり
構成や設計が完成した後は、いよいよデザイン・コーディング・公開のフェーズに進みます。
ここで重要なのは「スムーズな進行体制」と「公開後の初動チェック」です。
制作工程を軽視すると、意図と異なるLPが完成したり、成果測定に支障が出るリスクがあります。
制作時の注意点
・デザイナーやコーダーに「設計意図」を共有する(構成案+ペルソナ情報)
・フォントサイズ・配色・余白など、可読性や導線設計にこだわる
・レスポンシブ対応(PC・スマホ表示の最適化)は必須
公開時・初動のチェックポイント
・GoogleタグマネージャーやGA4などの計測タグ設置の確認
・フォーム送信やボタン動作など、UIまわりの動作確認
・早期にヒートマップやアナリティクスの数値を確認し、改善計画に備える
また、社内外の関係者との情報共有も成功の鍵です。公開までのスケジュール管理や、確認・承認フローの明確化により、トラブルを未然に防げます。
制作と公開はゴールではなく「運用のスタート地点」。最初の精度を上げておくことが、次のPDCAやA/Bテストの質を高めることにもつながります。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

WEBタノモーではリスティング広告を中心に、LP制作も承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。