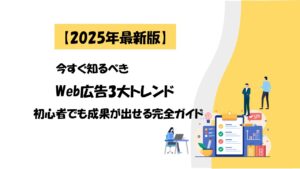WEB広告戦略
WEB TANOMOOO
データ分析からペルソナ構築へ:効果的なターゲティング戦略の立て方

ペルソナとは何か?その基本と重要性を理解する
語源「persona」に見るマーケティングへの影響
ラテン語の「persona」は、もともと古代ローマ劇場で俳優が用いた仮面や役割を意味していました。
この語源は、現代マーケティングにおける「ペルソナ」の概念にも影響を与えています。
マーケティングにおけるペルソナは、単なる顧客像ではなく、特定の行動パターンや価値観を持つ象徴的な存在として位置づけられています。
この象徴的な意味合いを取り入れることで、企業は顧客の多面的なニーズや心理を深く理解し、それに基づいた訴求や戦略の設計が可能となります。
ラテン語の起源を踏まえることで、マーケティングにおけるペルソナの重要性がより明確に理解できるでしょう。
心理学におけるペルソナの概念と現代マーケティング
心理学者カール・ユングは、ペルソナを「個人が社会に適応するために身につける仮面」と定義しました。
この概念は、個人が置かれた環境や相手に応じて役割を変えるという社会的適応の視点を含みます。
マーケティングにおけるペルソナ構築でも、この心理学的な視点が活かされています。
つまり、顧客がどのような環境に置かれ、どのような課題や感情を抱えているかを捉えることで、より現実的かつ共感を呼ぶ人物像を構築することが可能になります。
これにより、マーケティング施策全体の精度が大きく向上します。
マーケティングでのペルソナの役割と具体的活用法
マーケティングにおけるペルソナは、製品やサービスのターゲットとなる理想的な顧客像を明確にするツールです。
ペルソナを設計することで、ターゲティングの精度が上がり、施策の方向性も明確になります。
たとえば、若年層向けのブランドでは、20代前半女性のペルソナを設定し、好みに合ったビジュアルや訴求軸でSNS広告を展開することで、エンゲージメント率や購買率を高めることができます。
また、環境配慮型の製品を訴求する場合には、価値観に配慮したメッセージ設計が信頼感につながります。
さらに、以下のような施策においてペルソナは有効です。
・ターゲティング精度の向上(無駄な配信の削減)
・コミュニケーションメッセージの最適化(共感獲得)
・マルチチャネルでの接点設計(利用チャネルに応じた施策設計)
このように、ペルソナは顧客理解を深めるだけでなく、実際のマーケティング活動のすべての工程において重要な役割を担います。
ペルソナがビジネスに与える3つの効果
ターゲティング精度の向上と事例紹介
ペルソナを活用することで、ターゲティングの精度が飛躍的に向上します。具体的には、顧客像を明確にすることで広告配信や施策の対象を適切に絞り込み、費用対効果を高めることが可能となります。
たとえば、以下のようなツールや手法が有効です。
・Google Analytics:Webサイト訪問者の行動データを収集し、閲覧ページや滞在時間から興味関心を把握。
・CRMツール:購買履歴や問い合わせ内容などを一元管理し、顧客ごとのニーズや関心を明確化。
・セグメンテーション分析:属性・行動別に顧客を分類し、セグメントごとの施策を立案。
・A/Bテスト:異なる施策を実施・比較し、効果が高いパターンを特定。
実際の事例として、あるEコマース企業では、女性会社員を想定したペルソナに基づいて広告クリエイティブを最適化した結果、クリック率が約30%、コンバージョン率が約20%向上しました。これにより、広告費の最適化と売上拡大が同時に実現しています。
商品開発・サービス設計への具体的貢献
ペルソナは商品企画やサービス設計においても有効に機能します。具体的には、ペルソナのニーズや課題を反映させた製品仕様やサービス機能を構築することで、顧客満足度を高めることが可能です。
例として、30代のマーケティングマネージャーをペルソナに設定した場合、「忙しい日常でも時短できる利便性」や「直感的に使えるUI」が求められます。
こうしたインサイトを基に、UI設計やサポート機能の強化を行うことで、ニーズと設計の乖離を防ぐことができます。
さらに、サービス改善においてもペルソナが活用されます。
たとえば、「ニーズ把握が難しい」と感じるユーザーに向けて、リアルタイムなフィードバック収集機能やデータ可視化ツールの導入が実施され、ユーザーエクスペリエンスの向上に繋がった事例もあります。
施策の効率化とマーケティングROIの改善
適切なペルソナを設計することで、マーケティング施策全体の効率化が図れます。これは、ターゲットに合わせたメッセージの作成、チャネル選定、クリエイティブ制作などにおいて、無駄な工数やコストを削減できるためです。
特に以下の3点で大きな効果があります。
・施策の精度向上:ペルソナの課題や価値観に合った広告が設計可能になり、クリック率やエンゲージメントが向上。
・コンテンツの最適化:ペルソナごとに有効なフォーマット(動画・ブログ・資料)を選定することで、訴求効果を最大化。
・ROI改善:明確なターゲットに絞った配信が可能となるため、広告費の無駄を抑え、投資対効果が高まります。
また、これらは一度の施策にとどまらず、A/Bテストや定期的な見直しを通じて、継続的な改善サイクルを生み出す基盤となります。

効果的なペルソナ構築ステップ
定量データと定性データの違いと活用法
ペルソナ構築においては、「定量データ」と「定性データ」の両方をバランスよく活用することが重要です。定量データは数値で表現されるデータであり、統計的分析や傾向把握に適しています。一方、定性データはユーザーの感情や動機など、数値化しにくい情報を含むため、顧客心理の深い理解に役立ちます。
たとえば、以下のように使い分けると効果的です:
- 定量データ(例:訪問者数、コンバージョン率、購入履歴など):ターゲット層のボリューム感や行動傾向の把握。
- 定性データ(例:インタビュー結果、口コミ、問い合わせ内容など):ユーザーの価値観や動機、課題の深掘り。
これらを組み合わせることで、たとえば「都心在住・30代・業務効率を重視する」という定量データに、「毎朝の時間短縮を求めている」「UIにストレスを感じやすい」といった定性情報を加え、より精度の高い人物像を構築できます。
顧客情報の収集手法一覧(定性・定量)
効果的なペルソナ構築には、目的に応じた情報収集手法の選択が欠かせません。以下に主要な手法を分類して紹介します。
〈定性調査〉
・インタビュー:1対1またはグループ形式で実施し、価値観や感情、背景まで深く理解。
・フォーカスグループ:複数人での議論を通じて、潜在ニーズや反応を観察。
・自由回答式アンケート:定型化しにくい意見や個人的なエピソードを収集。
〈定量調査〉
・オンラインアンケート:短期間で大量の顧客データを取得可能。数値化により傾向が可視化しやすい。
・CRM分析:購買履歴、接点履歴、問い合わせ記録などを活用して顧客の行動傾向を把握。
・Web解析ツール(例:Google Analytics):ページ遷移、流入経路、デバイスなどのユーザー行動を定量的に収集。
〈その他の手法〉
・SNSの投稿分析:トレンドや感情を把握。例:InstagramやX(旧Twitter)などの言及分析。
・ウェビナーやオンラインイベントでのアンケート:リアルな声をその場で取得し、即時反映が可能。
これらを目的に応じて組み合わせることで、質の高いペルソナデータが得られ、戦略設計の精度が高まります。
分析ツールの活用と選定ポイント(SPSS・Tableauなど)
| ソフトウェア名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
|
SPSS |
統計解析に特化したソフト |
高度な統計処理が可能/信頼性が高い |
費用が高い/学習コストが高い |
|
Tableau |
データの可視化に強み |
直感的な操作/リアルタイム分析が可能 |
統計機能は限定的/大規模データに弱い |
|
Microsoft Power BI |
Microsoft製の統合BIツール |
Excelとの親和性が高い/導入コストが低い |
カスタマイズ性に制限あり/重い処理に弱い |
選定時の判断基準:
・目的(統計分析重視か、可視化重視か)
・予算(ライセンス費、社内導入コスト)
・操作性(チーム全体で運用可能か)
・既存ツールとの連携(CRMやGAとの統合性)
・技術サポートの有無(初期構築やトラブル対応)
これらを踏まえて最適なツールを選定し、収集データを構造化することで、説得力と一貫性のあるペルソナ設計が実現します。
ペルソナ設計時の具体的手法と注意点
基本属性と詳細設定のバランス
ペルソナ設計では、「誰に届けるか」を明確にするために、年齢・性別・職業・居住地などの基本的な属性情報が欠かせません。
これらはターゲット層の輪郭を描くための出発点となり、マーケティング施策の土台になります。
たとえば、「20代後半・未婚・都市部在住の女性会社員」という属性だけでも、通勤時間や情報収集手段、関心ジャンルなどにある程度の傾向が見えてきます。
一方で、細かすぎる設定は現実の顧客像と乖離しやすく、使い勝手を損なうリスクがあります。たとえば、「血液型」「毎朝飲む飲料」などは、施策と直結しない限り省略すべき項目です。
ポイントは「施策設計に有用か否か」を基準に情報を取捨選択することです。必要最小限かつ実用的な属性情報を設計し、マーケティング活動の一貫性と現実性を両立させましょう。
ユーザーの価値観・課題の可視化
ユーザー理解を深めるうえで、価値観や行動動機、直面する課題の明確化は不可欠です。以下のようなステップで、実際にマーケティング施策に活かせる情報を抽出できます。
1.インタビュー・アンケートの実施
顧客が「なぜその商品を選んだのか」「どんな不満を抱えているか」を直接問うことで、本音ベースの情報が得られます。
2.行動データの分析
ウェブサイトの離脱ページ、検索キーワード、購入フローの離脱点などから、潜在的な課題や不安要素が見えてきます。
3.心理的側面の構築
「なぜその価値観を重視するのか」「どのような感情が購買行動に影響しているか」といった深層心理を描くことで、ペルソナにリアリティが加わります。
これにより、施策設計時のコミュニケーションメッセージやUI改善などが、より的確で共感性の高いものになります。
カスタマージャーニーとの連携方法
ペルソナを活用する際は、カスタマージャーニーとの連携が非常に重要です。顧客が商品やサービスと出会い、購入・利用に至るまでのプロセスを可視化することで、どの段階で何を届けるべきかが明確になります。
以下の観点で設計しましょう。
・接点ごとの感情・課題の整理
認知→興味→比較→購入→継続の各段階で、ペルソナが抱える疑問や不安、期待を整理します。
・フェーズ別メッセージの設計
たとえば、認知段階では「共感を得るメッセージ」、購入段階では「安心感を与える具体的な根拠」が求められます。
・チャネルごとの最適化
認知フェーズはSNSや動画広告、比較段階ではオウンドメディアやLP、継続段階ではメールマーケティングやLINEなど、フェーズごとに接点を使い分けます。
このように、ペルソナとジャーニーを紐付けることで、顧客体験全体を設計でき、コンバージョンだけでなくLTV(顧客生涯価値)の向上にもつながります。

ペルソナ設計における落とし穴と見直しポイント
過剰な詳細設定を避けるための指針
ペルソナ設計では、情報を盛り込みすぎると、かえって現実のターゲットとかけ離れた理想像となり、活用しにくくなることがあります。これは使えないペルソナを生む典型例です。
以下の観点を意識し、適度な情報量に留めることが重要です。
・判断基準は「施策に使えるか」
たとえば「職業:IT企業のマーケティング職」は広告訴求設計に活かせますが、「好きな映画ジャンル」などは施策と無関係であれば省略すべきです。
・共有のしやすさを重視
現場の担当者がペルソナ資料を見て、すぐに活用できるレベルの簡潔さが理想です。たとえば「A4用紙1枚で収まるフォーマット」などが有効です。
・「こだわり」と「現実性」のバランス
情報の精度は高いほど良いですが、それが現実のデータに基づいていなければ、意味を成しません。仮説ベースでの設定も、検証可能な範囲に留めましょう。
市場の変化に合わせた定期的な見直し
ペルソナは一度作成したら終わりではなく、外部環境や消費者行動の変化に合わせて、定期的に更新する必要があります。特に以下のような状況では見直しが不可欠です。
・市場トレンドの変化:社会的関心の移り変わりや競合の出現により、価値観や行動が変化する可能性があります。
・新しい商品・サービスの投入:提供する内容が変われば、求められる価値や顧客層も変わるため、既存ペルソナが合わなくなることがあります。
・顧客からのフィードバック:アンケート結果やカスタマーサポートの声などから、「設定と実態のズレ」に気づくことがあります。
見直しの頻度は最低でも年1回、理想は四半期に1回程度が目安です。レビュー時には、既存ペルソナに加えるべき新要素や削除すべき項目を明確にし、改善履歴も記録しておくと便利です。
必要最小限のペルソナ数でスタートする
ペルソナは多ければ多いほど良いというものではありません。むしろ、最初は少数に絞り込むことで、施策の方向性がブレにくく、運用効率も高まります。
・推奨は3~4体程度から:対象サービスや事業規模にもよりますが、実用的には3~4パターンで十分です。それぞれに明確な差異を持たせましょう(例:性別、職業、デジタル行動など)。
・多すぎると施策が分散する:10体以上のペルソナを用意しても、それぞれに対して十分な施策を打つことが難しく、かえって成果が薄まる原因になります。
・最小構成でPDCAを回す:まずは少数で試験的に運用し、効果検証をしながら追加・更新していくことで、柔軟かつ現実的な運用体制が整います。
マーケティング施策への応用事例
広告配信におけるターゲティング最適化
ペルソナを活用した広告配信は、ターゲットへのリーチ精度と広告効果の最大化を図る上で極めて有効です。
以下の3ステップで最適化が可能です。
1.ペルソナ属性に基づいた配信設定
年齢・性別・職業・興味関心などの要素から、各広告媒体でのターゲティング設定を明確に行います。たとえば、子育て中の30代女性を対象とするなら、育児メディアやSNSコミュニティを通じた配信が有効です。
2.広告メッセージやクリエイティブの調整
ペルソナの課題や価値観に共感するような訴求内容に調整します。例:「時間がない」が課題であれば「1分で完結」などの文言を盛り込むことで反応率が向上します。
3.データ分析による運用改善
A/Bテストやクリック率・コンバージョン率の比較を通じて、どの訴求が効果的かを検証し、継続的な改善につなげます。
このように、ペルソナを軸にした広告配信は、媒体選定からクリエイティブ制作、配信後の改善まで、すべての工程においてロジカルな意思決定を支援します。
コンテンツマーケティングへの活用
ペルソナの活用は、コンテンツマーケティングでも大きな効果を発揮します。ユーザーのニーズや関心に合った情報を届けることで、エンゲージメントを高め、自然な形でのコンバージョンにつながります。
主な活用方法
・テーマとトーンの最適化
たとえば「20代の情報収集に積極的な層」には、カジュアルでフレンドリーな口調が効果的。一方、経営層向けコンテンツでは、論理性・信頼性を重視した文体が適しています。
・フォーマットの選定
忙しいビジネスパーソン向けには「1分で読める要約コンテンツ」、情報感度の高い層には「調査レポート」「ホワイトペーパー」など、ペルソナの情報消費スタイルに合わせた形式を選びます。
・事例紹介による信頼獲得
ペルソナと同じ課題を持つ人物の成功事例を紹介することで、信頼感を醸成できます。これは教育型コンテンツやLPにも応用可能です。
Web戦略(SEO・LP・A/Bテスト)の具体展開
ペルソナを基にWeb施策を設計することで、訪問者ごとのニーズに沿った体験を提供でき、CVR(コンバージョン率)の向上が期待されます。
・SEO施策への応用
ペルソナが検索しそうなキーワードを想定し、記事タイトルや見出しに反映させます。たとえば、「はじめての資産形成に不安を感じる30代女性」がターゲットなら、「初心者向け」「不安解消」などの文言が効果的です。
・ランディングページの設計
ペルソナの行動特性に合わせ、視線の流れ・コンテンツ順序・CTAボタンの設置位置を調整します。情報過多を避け、必要な情報に素早くアクセスできる構造が理想です。
・パーソナライズドA/Bテスト
異なるペルソナごとにメッセージやビジュアルを分岐させて検証することで、セグメント別に最適な表現を見極められます。
このように、Web施策はペルソナの設計精度と連動して成果が変わる領域であり、戦略的な連携が不可欠です。
チームと組織全体でのペルソナ活用
社内共有・理解促進のための仕組み
ペルソナの効果を最大化するには、マーケティング担当者だけでなく、営業、カスタマーサポート、商品開発など、組織全体で共通認識を持つことが重要です。部署間での足並みが揃っていないと、せっかく作成したペルソナも活用されずに形骸化してしまいます。
以下の取り組みが効果的です。
・ワークショップの実施
部門を横断してペルソナを検討・議論する場を設けることで、当事者意識が生まれ、理解が深まります。
・共有ドキュメントの整備
GoogleスライドやNotionなどのツールを用いて、常に最新のペルソナ情報にアクセスできる環境を構築します。A4 1ページ程度の簡潔な資料が理想です。
・定例ミーティングでの活用報告
施策ごとに「どのペルソナを前提に設計されたか」を共有することで、認識のズレを防ぎ、活用の定着を促進できます。
ペルソナがチームの共通言語になることで、施策の一貫性や社内連携が格段に向上します。
KPI設計と施策進捗管理の方法
ペルソナを活用したマーケティング施策を継続的に改善するためには、明確なKPI設計と進捗管理体制が不可欠です。
具体的なステップは以下のとおりです。
1.目標との関連性を明確化
たとえば、「CVRを10%改善」や「セミナー申込数を増加」など、各施策の成果目標をペルソナの行動特性と結びつけて設定します。
2.セグメント別のKPI管理
複数のペルソナを運用している場合は、ペルソナごとに成果を分けて管理し、施策ごとの相性や効果を分析します。
3.レビュー体制の構築
月次または四半期単位で、KPI進捗を可視化し、改善策の立案・実行までを一つのループとして回すことが重要です。GoogleデータポータルやLooker Studioなどの可視化ツールを活用すると効果的です。
進捗管理の精度を高めることで、施策が属人的にならず、組織全体で再現性あるPDCAが実現します。
全社展開に向けた教育と横展開施策
ペルソナを組織全体で活用するためには、継続的な教育と各部門での実践が求められます。以下の取り組みが有効です。
・社内研修の導入
新入社員や非マーケティング部門向けに、「ペルソナとは何か」「どのように活用するか」を解説する研修コンテンツを用意し、全社的な理解を促進します。
・各部門ごとの応用事例の紹介
営業部では「提案資料への活用」、サポート部では「対応フローの最適化」、開発部では「ユーザビリティテスト設計」など、業務に即した具体的な活用方法を共有します。
・成功事例の社内展開
特定部門でのペルソナ活用によって成果が出た場合は、社内報やミーティングで積極的に発信し、他部門への波及を促します。
このように、ペルソナはマーケティング部門の道具にとどまらず、顧客視点を持った全社的な意思決定のベースとなり得ます。
実践に役立つツール・テンプレートの紹介
Google AnalyticsやCRMツールの活用
ペルソナを構築するためには、顧客行動や属性情報を正確に把握できるツールの活用が不可欠です。中でもGoogle Analytics(GA)やCRMツールは、実用性と汎用性が高く、多くの企業で導入されています。
主な活用方法
・Google Analytics(GA)
訪問者の年齢層、デバイス、アクセス経路、行動フローなどを分析することで、ペルソナの行動傾向や関心領域を可視化できます。たとえば、「スマートフォンからの訪問が多い」「特定ページで離脱が多い」といった行動から、コンテンツ改善やデザイン設計のヒントが得られます。
・CRMツール(例:Salesforce、HubSpot)
顧客の属性・購入履歴・問い合わせ内容を一元管理し、ターゲットごとの傾向を分析できます。これにより、類似ユーザーの抽出やセグメント別のペルソナ構築が容易になります。
・ツール連携による分析の高度化
Google AnalyticsとCRMを連携させることで、オンライン行動と商談・購買などのオフライン情報を統合でき、より実態に近いペルソナを描くことが可能になります。
これらのツールを組み合わせることで、仮説ではなく、実データに基づいた信頼性の高いペルソナ構築が実現します。
汎用ペルソナテンプレートとカスタマイズ例
効率よくペルソナを設計するには、テンプレートの活用が非常に有効です。情報を体系的に整理できるだけでなく、チーム全体での共有や更新も容易になります。
基本テンプレートの構成要素(例)
・名前(仮名でOK)
・年齢・性別・職業・居住地などの属性
・目標・悩み・課題
・行動パターン(情報収集手段、意思決定プロセス)
・よく使うチャネル(SNS、検索、口コミなど)
・ブランドとの接点や期待する価値
カスタマイズのポイント
・業界ごとに必要項目を追加
たとえば、BtoB企業であれば「意思決定に関わる役職・人数」、医療系であれば「健康上の懸念」などを追加。
・フェーズ別に複数テンプレートを用意
「認知段階」「比較段階」「購入後」など、カスタマージャーニーの各段階に応じてペルソナを分けることで、施策との接続性が高まります。
・チームでの編集・更新がしやすい形式
GoogleスプレッドシートやNotionなど、リアルタイムでの共同編集が可能なツールで作成すると、部門横断での運用がしやすくなります。
データ分析ソフトウェアの選定基準と比較(SPSS・Tableau・Power BI)
| ソフトウェア | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
|
SPSS |
統計分析に特化。多変量解析などが可能 |
信頼性が高く、学術機関でも使われる/精密な分析が可能 |
操作が難しい/費用が高い |
|
Tableau |
データ可視化に特化。視覚的な操作が可能 |
インタラクティブなダッシュボードが作成できる |
統計分析には不向き/大規模データでやや重い |
|
Microsoft Power BI |
Microsoft製。Excelとの連携が強み |
コストパフォーマンスが高い/初学者にも扱いやすい |
複雑なモデリングやカスタマイズに限界あり |
選定時のチェックポイント
・使用目的:統計処理か、可視化か
・利用部門:マーケティング中心か、社内横断か
・スキルレベル:専門職か、一般社員か
・連携システム:GA、CRM、社内DBとの接続性
予算や目的に応じて最適なソリューションを導入することで、分析精度と実行力を同時に高められます。
成果に直結するペルソナ戦略
ペルソナ構築がもたらす長期的成果の整理
ペルソナを正しく構築・運用することで、単なるターゲット設定を超えた顧客理解が実現し、あらゆるマーケティング施策の質が向上します。
主な成果は以下のとおりです。
・施策の一貫性と効率化:社内で顧客像を統一して共有することで、広告、コンテンツ、営業活動まで一貫したアプローチが可能に。
・KPI達成率の向上:ターゲットに刺さる施策が打てるようになり、CVRやリード獲得数などが改善。
・商品・サービス開発の精度向上:開発段階で顧客ニーズを的確に捉え、競争優位性のあるプロダクトを構築できる。
このように、ペルソナは「顧客中心の戦略設計」の土台であり、成果に直結する意思決定の軸となります。
成功するターゲティング戦略の要件とベストプラクティス
効果的なターゲティング戦略を実現するには、単に属性情報を集めるだけでなく、ペルソナを活用した施策設計と運用体制が不可欠です。
成功のための要件は以下の3点に集約されます。
1.実データに基づく設計:仮説に偏らず、Web解析やCRMなどの客観データを組み合わせたペルソナを構築。
2.部門横断の活用:マーケティング部門だけでなく、営業・サポート・開発部門と連携して活用の幅を広げる。
3.PDCAによる継続的改善:定期的な見直しとフィードバックを取り入れ、常に最適な形に更新していく。
これらを意識することで、ターゲティングは絞り込む技術ではなく届けるべき価値を明確にする手法へと進化します。
今後のマーケティングにおける応用と展望
今後のマーケティング環境では、AIや機械学習を活用した「動的なペルソナ設計」や、データ連携による「リアルタイムパーソナライズ」が重要性を増していきます。
今後の展望として以下のポイントが挙げられます。
・AIによる自動ペルソナ生成:大量の行動データや購買履歴から、リアルタイムで最適なペルソナを自動構築する技術が普及。
・プラットフォームごとの細分化対応:Instagram・TikTokなど媒体ごとに行動様式が異なるため、それぞれに最適化されたペルソナの再定義が必要に。
・LTV重視型マーケティングへのシフト:短期的なCVではなく、中長期的な関係性構築を重視し、ペルソナ活用も継続支援やリピート戦略にシフト。
このような変化に対応するには、柔軟かつ拡張性のあるペルソナ設計を軸に、マーケティング全体の構造を見直していく必要があります。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。