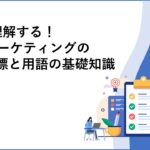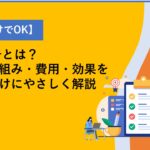マーケティング
WEB TANOMOOO
マーケティングとは?初心者でも分かる基礎知識と実践ステップ

マーケティングとは何か?
マーケティングの定義と特徴
販売促進や広告のような一部の業務だけでなく、市場調査、商品企画、価格設定、流通戦略、プロモーション、そして顧客との関係づくりまでを含みます。
重要なのは、「売るための仕組み」を設計すること。企業視点ではなく顧客視点での価値提供が中心にある点が特徴です。
インターネットを含む多様な手法の活用
たとえばテレビCM、チラシ、店舗POP、電話営業などの伝統的手法も、特定のターゲット層には効果的です。
重要なのは、それぞれの手法の特性を理解し、ターゲットや目的に合わせて最適な組み合わせで活用することです。
データ分析に基づく戦略立案の重要性
顧客の購買履歴、アンケート結果、広告反応、アクセス解析などのデータをもとに、現状の把握や課題発見、改善施策の立案が可能になります。
PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を繰り返すことで、マーケティング施策の精度は着実に向上していきます。
オンラインとオフラインの顧客接点の統合
顧客の購買行動は、オンラインとオフラインの両方をまたいで行われます。たとえば、「Webで商品を見てから店舗で購入する」「店頭で商品を確認し、後からECサイトで注文する」といった行動が一般化しています。そのため、マーケティング活動では両者を分けて考えるのではなく、一貫した顧客体験を提供する統合戦略(オムニチャネル戦略)が重要です。
具体的には、以下のような施策がオムニチャネル戦略に該当します。
・店舗での会員登録と連携したアプリの活用:リアル店舗で買い物した顧客にアプリを通じてポイントを付与し、次回以降のECサイトでの利用を促す。
・在庫連携システムの導入:店舗とECサイトで在庫状況を一元管理し、Web上で「最寄り店舗の在庫あり」を表示して来店を促す。
・クロスチャネルキャンペーンの実施:SNSやメールで配布したクーポンを店頭でも使用可能にすることで、チャネルをまたいだ購買を支援する。
こうした施策により、顧客はどのチャネルを利用しても同じブランド体験を得られ、企業側もより高度な顧客理解と購買促進が可能になります。
マーケティングの主な目的
顧客とのコミュニケーション強化
マーケティングの根幹にあるのは、顧客との信頼関係を築くことです。
単に商品を売ることだけが目的ではなく、企業やブランドが顧客と継続的に関係を築くことが求められます。
たとえば、SNSを活用した双方向のコミュニケーション、メールマーケティングによる定期的な情報提供、購入後のフォローアップなどは、顧客満足度を高め、ロイヤルティ向上にも寄与します。
こうしたコミュニケーションを通じて、顧客の声を製品改善やサービス向上に活かすこともマーケティングの重要な役割です。
集客から購買までのプロセス最適化
マーケティングの目的のひとつは、見込み顧客を効率よく集め、購買へと導くプロセスを最適化することです。具体的には、認知→興味→比較→購入という「購買ファネル」に沿って、段階ごとに最適なアプローチを行うことが重要です。
たとえば、認知段階ではWeb広告やSNS投稿を通じて商品やサービスの存在を知ってもらい、興味段階では資料ダウンロードや無料セミナーへの誘導などで理解を深めてもらいます。比較・検討段階では、導入事例やレビューの提供、購入段階ではクーポンや限定オファーなどが有効です。
このように、各フェーズでの適切な施策を設計することで、顧客の購買意欲を自然に高め、最終的なコンバージョン率の向上につなげることができます。
企業の収益向上とブランド価値の向上
マーケティングの最終的な目的は、企業の売上や利益の増加を実現することです。
しかし、単に商品を売るだけではなく、中長期的なブランド価値の向上を通じて、継続的な成長を目指すことが重要です。
例えば、価格競争に巻き込まれず、安定した利益率を保つためには、顧客にとって唯一無二の価値を提供するブランドの確立が欠かせません。
マーケティングでは、広告やPR活動、ストーリーテリング、SNSの発信などを活用し、企業の世界観や想いを顧客に伝えることで、ブランドの信頼性と好感度を高めていきます。
結果として、ブランド力が高まると新規顧客の獲得がしやすくなり、リピーターも増加し、広告費や販促コストを抑えつつ、企業の収益性が向上するという好循環を生み出すことができます。
マーケティングの基本を理解する
マーケティングの定義と役割
マーケティングとは、顧客のニーズを把握し、価値ある商品やサービスを開発・提供し、それを必要とする人々に届ける一連の活動を指します。
単なる販売促進ではなく、「誰に」「何を」「どうやって」届けるかという、戦略的な意思決定の中心にある業務です。
現代のマーケティングは、商品を売るための手法だけでなく、顧客の満足度を最大化し、企業の成長や社会的価値の創出に貢献することが求められています。
例えば、製品開発、価格設定、販路設計、プロモーション戦略などのすべてがマーケティング活動の一部であり、それらを統合的に設計することが成功への鍵です。
マーケティングの目的と企業への貢献
マーケティングの目的は、単に「売ること」ではありません。顧客のニーズを的確に把握し、それに応える価値を創出・提供することで、企業の持続的な成長と利益の最大化に貢献することが本質的な目的です。
企業においてマーケティングは、製品企画から販売後のフォローまで、事業全体を牽引する役割を果たします。特に近年では、市場環境の変化や顧客ニーズの多様化により、マーケティングの重要性はさらに増しています。
具体的には、マーケティングが成果を出すことで以下のような貢献が期待されます。
・売上や利益の向上
・ブランド力の強化
・顧客との信頼関係の構築
・新規市場の開拓や事業の多角化
・社内の企画・開発・営業の方向性を統一
マーケティングは、企業の目指すビジョンと顧客の期待をつなぐ橋渡し役として、経営の中核に位置する活動です。
顧客との関係構築とCRMの重要性
マーケティングにおいて、商品を「売ること」以上に重要なのが、顧客との継続的な関係構築です。
その中心的な考え方がCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)です。
CRMは、顧客一人ひとりの属性や購買履歴、接触履歴などの情報を蓄積・活用し、よりパーソナライズされたコミュニケーションを行うための仕組みです。
これにより、顧客満足度やロイヤリティを高め、再購入や紹介といった長期的な価値を生み出すことが可能になります。
たとえば、購入後のフォローメールやバースデークーポンの配信、LINEやSNSによる顧客との双方向コミュニケーションは、CRMの一例です。
こうした施策は、短期的な売上だけでなく、顧客との信頼関係を強化し、安定的な収益基盤を築く上でも欠かせません。
価値を創造・提供するプロセスの流れ
マーケティングは、商品やサービスの「販売」ではなく、「価値の創造と提供」を軸に展開されます。この価値創造のプロセスは、以下のような一連のステップで構成されます。
1.市場調査とニーズ把握
ターゲットとなる顧客の課題や欲求を調査・分析し、どのような価値が求められているかを明らかにします。
2.価値提案の設計(バリュープロポジション)
競合と差別化できる独自の価値を定義し、「なぜ顧客が自社を選ぶべきか」を明確にします。
3.製品・サービスの開発と価格設定
提供価値に応じた商品やサービスを具体化し、適正な価格戦略を設計します。
4.チャネル・プロモーションの最適化
顧客に効果的に届く流通チャネルと、魅力的な伝え方(広告・PR・コンテンツ等)を選定・実施します。
5.提供後のフォローと改善
提供後の顧客満足度を測定し、リピートや紹介につなげるための改善を継続します。
このように、マーケティングは単なる施策ではなく、一貫した「価値提供の流れ」として設計・運用されるべきものです。
マーケティングが果たす役割と企業成長への影響
マーケティングは、単に商品を広めるための手法にとどまらず、企業全体の成長を左右する戦略的な役割を担います。
顧客のニーズや市場の変化を的確に捉え、それに応じた商品開発・ブランディング・販売促進までを統合的に設計することが、企業の競争力向上や中長期的な収益の最大化につながるのです。
とくに現在の市場環境では、商品力や価格だけでは他社との差別化が難しいため、顧客との関係性の強化やブランド価値の醸成が成長の鍵になります。
そのためマーケティング部門は、営業・商品開発・カスタマーサポートなど他部署とも連携し、企業の方向性をリードする重要な役割を担っています。
この章では、組織内でのマーケティングの位置づけや、顧客中心の戦略立案によって企業にもたらされる具体的な効果について詳しく解説します。
組織内におけるマーケティングの位置づけ
マーケティングは「広報や広告だけの業務」と誤解されがちですが、実際には企業全体の戦略を支える中核機能です。現代のビジネスでは、商品企画・営業・サービス提供・顧客フォローまで、あらゆる部門がマーケティングと関係しています。
特にマーケティング部門は、以下のような役割を担います。
・市場調査や顧客データをもとに事業方針を設計する機能
・営業部門と連携してターゲット層への適切なアプローチを立案
・ブランディングやカスタマーエクスペリエンス(CX)を主導する立場
このように、マーケティングは経営層と現場の橋渡しを行い、企業の意思決定に重要な影響を与えるポジションにあります。したがって、マーケターは“消費者視点”と“ビジネス視点”の両方を持ち、組織全体を巻き込む役割を果たす必要があります。
顧客ニーズを満たす戦略の立て方
マーケティングにおいて、成功の鍵を握るのは「顧客ニーズの的確な把握」と「それに基づいた戦略設計」です。
商品やサービスを提供する側の都合ではなく、顧客が本当に求めている価値は何かを出発点に考える必要があります。
顧客ニーズを捉えるための代表的なアプローチは以下の通りです。
・アンケート調査やインタビューによる定性情報の収集
・購買履歴や行動データなどの定量データの分析
・ペルソナ(仮想の顧客像)やカスタマージャーニーによる行動予測
このような情報をもとに、「どの市場に対して」「どんな課題を解決し」「どのようにアプローチするか」を明確に定義し、製品開発・プロモーション・販売チャネルまでを一貫させた戦略を立てることが重要です。
たとえば、働く女性をターゲットにした化粧品では、「時短」「多機能」「持ち運びやすさ」といったニーズを満たす商品設計や、SNS中心のプロモーション展開が有効なケースもあります。
競争力を高めるマーケティング戦略の実践例
競争の激しい市場環境では、自社の強みを活かしながら他社との差別化を図る戦略が求められます。マーケティングにおける競争力とは、「選ばれる理由」を明確にし、それを一貫して顧客に伝える力でもあります。
以下は、競争力を高めた実践的な戦略の例です。
① ニッチ戦略(特定市場に特化する)
例:高齢者向けスマートフォンのように、汎用品ではなく「特定の顧客層に絞った製品・サービス」を展開することで、高い満足度と競争優位性を実現。
② ブランディング強化
例:アパレルブランドが「サステナブル素材」を打ち出し、環境意識の高い層に支持される。ロゴ・ビジュアル・世界観の一貫性が差別化要因になる。
③ 顧客体験(CX)の最適化
例:ECサイトでの「パーソナライズされたおすすめ商品」や「購入後のフォローアップメール」によって、再購入率が向上。
これらの戦略は、単体で効果を発揮するのではなく、商品企画・価格設定・プロモーション・販売チャネルなどと連動して設計されることが重要です。

マーケティングの主な分類とアプローチの違い
BtoCマーケティングとBtoBマーケティングの違い
BtoC(Business to Consumer)は、一般消費者を対象としたマーケティングで、感情や印象が購買に大きく影響します。
短期間での意思決定が多く、広告やSNS、キャンペーンの影響を受けやすいのが特徴です。
一方、BtoB(Business to Business)は、企業を相手にしたマーケティングであり、論理的な判断や長期的な関係構築が重要です。
営業活動、業界展示会、ホワイトペーパーなど、信頼や実績を重視したアプローチが中心となります。
| 観点 | BtoCマーケティング | BtoBマーケティング |
|---|---|---|
|
顧客 |
一般消費者 |
企業担当者や意思決定層 |
|
購買判断 |
感情・印象重視 |
論理・ROI重視 |
|
購買期間 |
短い |
長い(比較・検討) |
|
主な手法 |
広告・SNS・セール |
営業・提案・資料提供 |
両者では施策の設計やKPIも異なるため、自社のターゲットに応じて最適な手法を選択する必要があります。
ソーシャルマーケティングと社会的価値
ソーシャルマーケティングとは、企業利益を追求するだけでなく、社会課題の解決や公共の利益に貢献することを目的としたマーケティング手法です。
商業的マーケティングとは異なり、「社会的な行動変容」や「公共意識の醸成」に重きを置きます。
代表的な例:
・行政や自治体による「禁煙キャンペーン」や「交通安全運動」などの公共啓発活動
・企業による「プラスチック削減活動」や「子ども食堂の支援」といったCSR(企業の社会的責任)活動
・SDGs(持続可能な開発目標)を反映した企業ブランディングや製品展開
これらは、企業の社会的責任(CSR)や持続可能性への取り組みと密接に関係しており、消費者の共感や信頼の獲得にもつながります。
近年はZ世代など社会貢献意識の高い層を意識し、ブランディングや採用戦略にも活用されるケースが増えています。
マスマーケティングとダイレクトマーケティングの比較
マスマーケティングは、テレビCMや新聞広告、屋外広告などを用いて、幅広い層に一斉にアプローチする手法です。
認知拡大やブランド構築に適しており、大企業やナショナルブランドで多く活用されています。
一方、ダイレクトマーケティングは、個別のターゲットに対して直接的な訴求を行う手法です。
DM(ダイレクトメール)やメールマーケティング、LINE配信、Web広告などが該当し、特定のセグメントにパーソナライズされたメッセージを届けられる点が特徴です。
| 項目 | マスマーケティング | ダイレクトマーケティング |
|---|---|---|
|
ターゲット |
不特定多数 |
特定の個人・属性層 |
|
目的 |
認知拡大・ブランド構築 |
反応・成果(CV) |
|
メディア例 |
テレビ、新聞、雑誌 |
メール、SNS広告、DM |
|
効果測定 |
困難な場合が多い |
数値で測定しやすい |
近年では、ブランド認知をマスマーケティングで行い、ダイレクトマーケティングで獲得につなげるといった組み合わせも主流になっています。
マーケティング目的と費用対効果をふまえた戦略設計が重要です。
3C分析(顧客・競合・自社)の実施方法
3C分析は、Customer(顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)の3つの視点から自社のマーケティング戦略を検討する代表的なフレームワークです。それぞれの要素を体系的に分析することで、市場における自社の立ち位置を明確にできます。
3つの視点の概要
・顧客(Customer):ターゲット層のニーズ、行動、価値観、購買プロセスなど
・競合(Competitor):競合他社のシェア、商品力、サービスの強み・弱み、戦略
・自社(Company):自社の強み(USP)、リソース、ブランド価値、課題など
分析例:地域密着型フィットネスジムの場合
・顧客(Customer)
→ 健康志向の高い30~50代がメインターゲット。価格よりも「通いやすさ」や「スタッフ対応の良さ」を重視。SNSでの情報収集が活発。
・競合(Competitor)
→ 全国チェーンの大手ジムが駅前に立地。最新マシンや豊富なプログラムを訴求しているが、個別対応が手薄でサポートに不満の声あり。
・自社(Company)
→ 地元に根付いた運営で、スタッフによる丁寧な指導とアットホームな雰囲気が強み。施設の老朽化が課題。
この分析結果をもとに、「個別対応」や「地域密着」などの差別化要素を前面に出した訴求戦略が有効となります。
4P・4C分析による戦術構築
マーケティング戦略を立案する際には、「4P分析」と「4C分析」を組み合わせて活用することが効果的です。
4Pは企業視点からのマーケティング戦略を構築するフレームワークであり、4Cは顧客視点から価値を考える枠組みです。
この両者を照らし合わせてバランスを取ることで、実践的で成果につながる戦術を組み立てることが可能となります。
■ 4P分析(企業視点の要素)
・Product(製品・サービス):どのような価値ある商品やサービスを提供するか
・Price(価格):どのような価格設定にするか
・Place(流通):どのチャネルで商品・サービスを提供するか
・Promotion(販促):どのように顧客へ認知・理解・興味喚起を促すか
■ 4C分析(顧客視点の要素)
・Customer Value(顧客価値):顧客がその商品やサービスから得られる価値は何か
・Cost(顧客負担):価格だけでなく、時間や手間などの総コストはどれほどか
・Convenience(利便性):顧客が購入・利用しやすい導線は整っているか
・Communication(対話・信頼構築):双方向のコミュニケーションが取れているか
■ 4Pと4Cを組み合わせた戦略立案の考え方
| 4P(企業視点) | 対応する4C(顧客視点) | 戦略立案の視点例 |
|---|---|---|
|
Product(製品) |
Customer Value(顧客価値) |
「高性能」ではなく「時短できる」「失敗しない」といった価値訴求ができているか? |
|
Price(価格) |
Cost(顧客の負担) |
単価の安さではなく、「購入に手間がかからない」「維持コストが低い」なども考慮しているか? |
|
Place(流通) |
Convenience(利便性) |
店舗受け取り・自宅配送・即日対応など、選べる手段を提供できているか? |
|
Promotion(販促) |
Communication(対話) |
一方的な広告ではなく、SNSでのコメント返信やチャットボットなどで対話できているか? |
このように、企業の施策(4P)を顧客視点(4C)で検証することで、より説得力のある施策に落とし込むことができます。
■ 分析例:住宅リフォームサービスの場合
・Product × Customer Value:間取り変更や断熱強化などの機能面だけでなく、「家族の快適な暮らしを実現する」といった情緒的価値を訴求。
・Price × Cost:単にリフォーム費用だけでなく、補助金活用の提案や長期的な光熱費削減といった観点も加味。
・Place × Convenience:オンライン相談、現地見積もり予約、LINEでの進捗共有など導線設計を工夫。
・Promotion × Communication:施工前後のストーリーをSNSで共有し、過去の施主の声も交えた対話型コンテンツを展開。
このような視点で4Pと4Cを往復することで、顧客満足と企業成果の両立が実現しやすくなります。
SWOTとPESTによる内部・外部環境の可視化
マーケティング戦略を設計する上で欠かせないのが、「自社の立ち位置」を客観的に把握することです。そのための代表的なフレームワークがSWOT分析とPEST分析です。これらは、内部要因と外部要因の両面から企業環境を整理し、適切な戦略判断を支える役割を果たします。
■ SWOT分析:企業の内部・外部要因を整理する
SWOT分析は、以下の4つの視点から現状を整理します。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
|
Strength(強み) |
他社にない技術力、ブランド力、顧客基盤など |
|
Weakness(弱み) |
人材不足、広告予算の少なさ、認知度の低さなど |
|
Opportunity(機会) |
市場拡大、ニーズの多様化、補助金政策など |
|
Threat(脅威) |
新規競合の出現、法規制の変更、経済不況など |
この分析を行うことで、強みを活かし、弱みを補完し、機会を捉え、脅威に備えるという基本戦略が明確になります。
■ PEST分析:外部環境の変化を俯瞰する
PEST分析は、社会全体のマクロ環境を以下の4つの要素で整理する方法です。
| 要素 | 検討ポイントの例 |
|---|---|
|
Politics(政治) |
規制緩和・補助金制度・地方自治体の施策など |
|
Economy(経済) |
景気動向、物価、為替、金利、消費傾向など |
|
Society(社会) |
少子高齢化、ライフスタイルの変化、健康志向など |
|
Technology(技術) |
AI、IoT、キャッシュレス化、SNSの普及など |
これにより、市場の変化要因やトレンドを先読みしやすくなり、長期的なマーケティング施策の方向性を定める判断材料となります。
■ 分析活用のポイント
・SWOTとPESTはセットで使うと効果的です。たとえば、「PESTで捉えた技術トレンド」を「SWOTのOpportunity」に取り込むことで、現実的なチャンスを具体的な戦術につなげることができます。
・分析結果は施策アイデアの源泉になるだけでなく、経営層への提案資料としても活用可能です。
マーケティングの基本手法とチャネル戦略
マーケティングミックス(4P)の具体的な役割
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
Product(製品) |
顧客のニーズを満たす製品・サービスの設計。品質、機能、デザイン、ブランド、アフターサポートなどを含む。 |
|
Price(価格) |
市場や競合、原価を踏まえた適切な価格設定。値引き、分割払い、サブスクリプションモデルなども含む。 |
|
Place(流通) |
商品・サービスをどこでどのように提供するか。実店舗、ECサイト、代理店などの流通チャネル。 |
|
Promotion(販促) |
顧客に製品の価値を伝える手段。広告、SNS、イベント、DM、口コミなどが代表例。 |
オンラインとオフラインを融合させたオムニチャネル戦略
現代のマーケティングでは、「オンライン(デジタル)」と「オフライン(リアル)」を分断せず、統合的に運用すること=オムニチャネル戦略が重要視されています。顧客は複数の接点を通じて情報収集や購買を行うため、企業側もそれに対応する体制が求められます。
■ オムニチャネル戦略の具体例
・アパレル業界:ユーザーがECサイトで商品を確認 → 実店舗で試着 → オンラインで購入。
・飲食業界:SNSでプロモーション → モバイルオーダー → 店頭受け取り。
・小売業界:Web広告で新商品を認知 → チラシで再確認 → 実店舗で体験 → ポイントカードアプリで再来店誘導。
このように、顧客視点での一貫した体験設計を行うことが、LTV(顧客生涯価値)の向上やブランドロイヤルティの醸成につながります。
マーケティングが果たす役割と企業成長への影響
組織内におけるマーケティングの位置づけ
マーケティングは「広報」や「広告」だけでなく、事業戦略の中核を担う存在です。単なる集客活動ではなく、商品企画、顧客理解、販売促進、ブランド形成まで、社内のあらゆる部署と連携しながら活動する必要があります。
たとえば、製品開発部門とは顧客ニーズをもとにした商品改善に関わり、営業部門とはリードの質向上や顧客フォローに関して密に連携します。このように、マーケティングは部門横断的な戦略推進役として、組織のパフォーマンス全体を高める役割を果たしています。
顧客ニーズを満たす戦略の立て方
企業が成長するには、単に商品を販売するだけではなく、「顧客が本当に求めているもの」を正しく理解し、それを満たす戦略を構築することが不可欠です。
・ペルソナ設計:ターゲットとなる顧客像を明確にし、課題や価値観を把握
・カスタマージャーニーの作成:顧客が情報を得て、購買・利用するまでのプロセスを可視化
・ソリューション提案型戦略:商品の機能ではなく、顧客の課題解決やベネフィットを重視した訴求
このようなアプローチにより、顧客満足と企業収益の両立が可能になります。
競争力を高めるマーケティング戦略の実践例
市場で競合他社に打ち勝つには、**他社にはない強み(差別化)**を活かしたマーケティング戦略が鍵となります。
■ 実践的な事例(提案事例として記載)
・中小製造業A社:競合が価格訴求する中、「高品質・短納期」の強みを前面に打ち出したWeb広告で受注件数を拡大
・不動産会社B社:ポータル依存から脱却し、自社サイトとLINEを活用した地元密着型の集客施策で問合せ数が増加
・美容室C社:GoogleビジネスプロフィールとInstagramを連携し、地域検索+SNS経由の来店を同時に獲得
このように、競争力を発揮するためには、自社の資源・強みを明確にした上での一貫したマーケティング施策が重要です。

マーケティングの主な分類とアプローチの違い
BtoCマーケティングとBtoBマーケティングの違い
マーケティングは、対象となる顧客が「個人(BtoC)」か「法人(BtoB)」かによって、戦略や施策の設計が大きく異なります。
・BtoC(Business to Consumer)
対象:個人消費者
購買決定のスピードが速く、感情的な要素が重視されやすい
例:テレビCM、SNS広告、クーポン配布など
・BtoB(Business to Business)
対象:法人顧客やビジネス関係者
購買には複数の意思決定者が関与し、比較検討のプロセスが長い
例:展示会、ホワイトペーパー、メールマーケティングなど
それぞれのマーケティングでは、訴求ポイント・チャネル・コンテンツの設計を最適化することが重要です。
ソーシャルマーケティングと社会的価値
ソーシャルマーケティングとは、営利目的に限らず、社会全体の行動変容や価値創造を目指すマーケティング手法です。公共性の高い領域で使われることが多く、行政や非営利団体も積極的に活用しています。
例:
環境保護を促すリサイクル活動の啓発キャンペーン
禁煙推進や交通安全啓発などの公的プロジェクト
SDGs(持続可能な開発目標)に関連した企業の取り組み
マスマーケティングとダイレクトマーケティングの比較
| 項目 | マスマーケティング | ダイレクトマーケティング |
|---|---|---|
|
対象 |
不特定多数 |
特定の個人やセグメント |
|
メディア |
テレビCM、新聞、ラジオなど |
DM、メール、SNS広告、LINE等 |
|
目的 |
認知度向上、ブランド形成 |
コンバージョン獲得、関係構築 |
|
特徴 |
大規模で広範囲、即効性は低い |
ターゲット明確、測定・改善しやすい |
例えば、新商品の全国認知を広げる場合はマス広告、既存顧客にリピート購入を促すならダイレクト施策が適しています。
代表的なマーケティング分析手法の活用
3C分析(顧客・競合・自社)の実施方法
3C分析とは、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から市場環境を分析し、マーケティング戦略を立案するフレームワークです。
・Customer(顧客):誰が顧客なのか、どのようなニーズや行動特性を持っているのか
・Competitor(競合):競合他社の強み・弱み、シェア、価格、商品戦略など
・Company(自社):自社のリソース、技術力、ブランド力、販売網など
たとえば、住宅リフォーム業界においては、顧客は30〜50代の持ち家層が中心で、競合は地域密着型の工務店、自社は長年の施工実績が強み、といった分析が可能です。これにより、自社に最適な訴求ポイントや差別化の切り口が明確になります。
4P・4C分析による戦術構築
| 4P(企業視点) | 4C(顧客視点) |
|---|---|
|
Product(製品) |
Customer Value(顧客価値) |
|
Price(価格) |
Cost(顧客の負担) |
|
Place(流通) |
Convenience(利便性) |
|
Promotion(販売促進) |
Communication(対話) |
たとえば、英会話教室のプロモーションでは、4Pでは「無料体験のチラシ配布」ですが、4Cで見ると「学びやすい時間帯での開講」や「LINEでの質問対応」など、より顧客本位の設計が求められます。
このように、4Pだけでなく4Cの観点を加えることで、顧客ニーズとのズレを防ぎ、実行力のある戦術構築が可能となります。
SWOTとPESTによる内部・外部環境の可視化
SWOT分析とPEST分析は、自社の強み・弱み、そして外部環境の変化を可視化するためのフレームワークです。
SWOT分析:
S(Strength):強み
W(Weakness):弱み
O(Opportunity):機会(市場の成長性や技術革新など)
T(Threat):脅威(競争激化や法改正など)
PEST分析:
P(Politics):政治・法律
E(Economy):経済状況
S(Society):社会・文化の動向
T(Technology):技術革新やIT環境の変化
たとえば、中小製造業であれば、SWOTで「高い技術力(S)」「販路の少なさ(W)」を洗い出し、PESTでは「円安による輸出有利(O)」「エネルギーコスト増(T)」といった分析が可能です。
これらを組み合わせることで、戦略立案におけるリスクとチャンスを客観的に把握でき、持続可能な成長につながります。
成果を最大化するための効果測定と改善手法
KPIとKGIの関係性と設定方法
マーケティング施策を効果的に運用するには、定量的な目標管理が欠かせません。特に、KGI(最終目標)とKPI(達成指標)の設定は、活動の方向性と進捗状況を明確にするために重要です。
・KGI(Key Goal Indicator):最終的な成果指標。例:月間100件の資料請求、売上1,000万円達成など。
・KPI(Key Performance Indicator):そのKGI達成に必要な中間指標。例:月間サイト訪問数1万件、CVR3%以上、広告クリック率2%など。
たとえば、不動産サイト運営企業の場合、「KGI=資料請求数100件」に対して、「KPI=LP閲覧数3,000件、CVR3.3%」などを設定し、広告施策やSEOの改善に活用します。
KPIの設定にはSMART原則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)を意識すると効果的です。
PDCAとOODAの活用による継続改善
マーケティング活動は、一度の施策で成果を出すのではなく、継続的な改善を通じて精度を高めていくことが重要です。その際に有効なのがPDCAとOODAのフレームワークです。
・PDCA(Plan → Do → Check → Act):計画・実行・検証・改善の循環型モデル。広告配信やSEO施策など反復業務に適しています。
・OODA(Observe → Orient → Decide → Act):観察・状況理解・意思決定・実行を迅速に行うモデル。競合や市場変化に柔軟に対応する際に効果的です。
データを活用した改善の具体例
実際のマーケティング施策では、分析結果をもとに改善施策へつなげるプロセスが成功のカギとなります。
■ 具体例(提案事例)
・Web広告:クリック率(CTR)が低い → 広告クリエイティブを差し替え → CTRが1.2% → 1.8%に向上
・LP(ランディングページ):離脱率が高い → ファーストビューの訴求改善 → 平均滞在時間が40秒 → 1分20秒に改善
・SNS:エンゲージメント率が低下 → 投稿内容を「お役立ち系」中心に再設計 → いいね数が30%増加
こうした数値をもとに仮説と検証を繰り返すことで、戦略の精度が高まり、マーケティングROIが向上します。

マーケティング活動の未来と成長への展望
デジタルシフトとAI活用の加速
す。特に以下の分野で変革が加速しています。
・パーソナライズド広告:ユーザーの行動履歴や興味関心に基づき、AIが最適な広告を自動生成・配信
・チャットボットの導入:問い合わせ対応や商品案内を自動化し、24時間のカスタマーサポートを実現
・需要予測とレコメンド:ECサイトでは購買履歴を分析し、次に買う商品を高精度で提案
このように、AIを活用することで人間の作業負荷を軽減しながらも、精度の高いターゲティングとCX(顧客体験)向上が可能になります。
サステナブルマーケティングとブランド価値
マーケティング活動は今後、社会的責任(CSR)や持続可能性(SDGs)との連携がより重要になります。単なる売上拡大ではなく、「何のためにマーケティングをするのか」という価値観が問われる時代です。
・例:再生可能素材を使ったパッケージを訴求する企業
・例:地域貢献を前面に出したブランディングで、顧客との信頼関係を構築するNPO
こうした活動は短期的な利益よりも、長期的なブランドロイヤリティの向上やファンの獲得につながります。
学び続ける姿勢が差を生む
マーケティングは日々進化しています。SNSのアルゴリズムや検索エンジンの仕様変更、法律・規制のアップデートなど、常に情報をキャッチアップする必要があります。
そのため、マーケターには次のような姿勢が求められます。
・継続的なインプット(書籍・セミナー・業界ニュース)
・小さな仮説検証の積み重ね(ABテストや施策の見直し)
・チーム内でのナレッジ共有とPDCA文化の醸成
変化に対応できる柔軟性と、試行錯誤を楽しむ姿勢が、成果を伸ばす鍵となるでしょう。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。