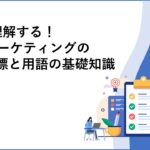マーケティング
WEB TANOMOOO
【実践ガイド】ChatGPTで効率化!AI活用×市場シェア回復の競合分析5ステップ戦略

競合分析は、今やビジネスにおける基本動作とも言える重要なプロセスです。
しかし、膨大な情報を収集し、意味のある形に整理する作業には、多大な時間と労力が必要です。
そこで注目を集めているのが、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用です。
本ガイドでは、AIを取り入れた最新の競合分析手法から、SWOTや3Cといった基本フレームワークの活用、市場シェアを回復するための具体的な施策設計まで、体系的に解説します。
初心者から中級マーケターまで、すぐに実務に応用できる知識とノウハウを提供します。
競合分析の基本を理解する
特に市場シェアの回復や拡大を目指すうえで、競合の理解は欠かせません。
このセクションでは、競合分析の定義や目的、基本的な種類について整理し、初学者でも迷わず実践に移せる基礎知識を紹介します。
競合分析とは何か
競合分析とは、同一市場内で活動する他社の戦略、製品、サービス、マーケティング手法などを多角的に調査・評価し、自社の戦略に反映させるためのプロセスです。単なる情報収集ではなく、自社との比較を通じて「何が強みになりうるか」「どこに改善余地があるか」を見極めることが主な目的です。
たとえば、競合他社が高価格帯商品を主力としているならば、自社が中価格帯で勝負する戦略が見えてくるなど、競合のポジショニングによって自社の立ち位置を再設計することが可能になります。
競合分析の目的と重要性
競合分析の目的は、以下の3つに集約されます。
1.市場の現状把握
自社が置かれている市場環境を、客観的かつ定量的に理解する。
2.自社のポジションの明確化
顧客に対してどのような価値を提供できるのか、競合と比較して何が優れているかを把握する。
3.戦略の立案と改善
競合の強みや失敗事例を踏まえたうえで、より有効なプロモーション施策や商品改善に結びつける。
また、競合分析は単発で終えるものではなく、定期的に行うことで市場変化に対応する柔軟性を持てるという点でも重要です。
競合企業の種類:直接・間接・代替・検索結果での競合
競合にはいくつかのタイプがあり、対象によって分析の視点も異なります。
・直接競合:まったく同じ商品・サービスを同じターゲットに提供している企業。例:UberとLyft
・間接競合:カテゴリは同じだがターゲットや価格帯が異なる企業。例:スターバックスとコンビニのコーヒー
・代替競合:顧客ニーズを別の手段で満たす商品を扱う企業。例:ジムとオンラインフィットネスアプリ
・検索競合(SEO競合):同じキーワードで検索結果に出てくるWeb上の競合サイト
これらを分類して把握することで、どの競合に重点的に対抗すべきかを判断しやすくなります。
競合分析が市場シェア回復に与える影響
競合分析を通じて得たインサイトを活用することで、自社は以下のような戦略的アクションを取ることができます。
・差別化戦略の構築:競合がカバーしていないニーズを見つけ、独自の価値を打ち出す。
・強みの強化:競合に勝っている分野(例:カスタマーサポート)をさらに強化してブランド力を高める。
・弱みの補完:競合の成功施策を参考に、自社の改善点を具体化する。
例えば、ある企業が競合他社の価格帯と広告戦略を分析し、「高価格帯では勝てない」と判断したうえで、低価格かつ簡素なサービス提供に切り替えた結果、若年層を中心に市場シェアを拡大した事例もあります。
競合を知り、自社を知ることが、継続的なシェア回復の出発点になります。
競合分析のフレームワーク
このセクションでは、マーケティングや経営戦略の現場で広く使われている代表的な3つの分析手法──5フォース分析、SWOT分析、3C分析──について解説します。
目的や状況に応じてこれらを使い分けることで、精度の高い競合分析が可能になります。
5フォース分析の活用方法
5フォース分析(ファイブフォース分析)は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した、業界の競争構造を分析するためのフレームワークです。以下の5つの視点から市場の競争要因を多角的に評価します。
1.新規参入者の脅威
業界に新しい企業が参入しやすいかどうか。参入障壁が低いと、既存企業のシェアが奪われやすくなります。
2.代替品の脅威
顧客が代替商品や他カテゴリのサービスに乗り換える可能性。技術革新や消費者の志向変化が要因となります。
3.買い手の交渉力
顧客が価格や品質について交渉力を持つかどうか。BtoBでは大口取引先が影響力を持つことも多いです。
4.供給者の交渉力
仕入れ先が価格や供給条件をコントロールできるか。独占的な供給元がある場合、コスト面でリスクになります。
5.業界内の競争の激しさ
同業他社間の価格競争や差別化の状況。競合が多く、製品の差が小さい業界では競争が激化します。
これらを分析することで、市場の魅力度(儲かりやすさ)や、自社が置かれている競争環境の厳しさを判断することができます。定期的に業界構造を見直すことで、新たな脅威や機会を早期に察知できるようになります。
SWOT分析で自社と競合を比較する
| 分類 | 内容の例 |
|---|---|
|
強み |
自社独自の技術、ブランド力、カスタマーサポートの質 |
|
弱み |
認知度の低さ、人材不足、Web集客の弱さ |
|
機会 |
業界の成長トレンド、新たなニーズ層の出現 |
|
脅威 |
新規参入者の増加、競合の価格攻勢、規制強化 |
競合と自社のSWOTを並列比較することで、「何が差別化要素になるか」「どこを改善すべきか」が見えてきます。また、強みと機会を掛け合わせることで、新製品開発や市場拡大の具体的なアクションに落とし込むことが可能です。
3C分析による顧客・競合・自社の関係性の把握
3C分析は、「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3者関係を整理し、自社が提供すべき価値の方向性を導くフレームワークです。
・Customer(顧客):誰が、何を求めているのか。セグメントごとのニーズ・課題・購買動機を明確にします。
・Competitor(競合):競合はどんな強み・戦略でアプローチしているか。ポジショニングや価格、チャネル戦略を比較。
・Company(自社):自社の提供価値は何か。リソース、ブランド、商品力を踏まえ、勝てる領域を探ります。
この3つの視点が重なる領域、つまり「顧客が求めていて、競合が提供できず、自社が対応できる価値領域」が競争優位を築くヒントになります。3C分析は商品開発やコンセプト設計、マーケティング施策の方向性を検討する際にも有効です。
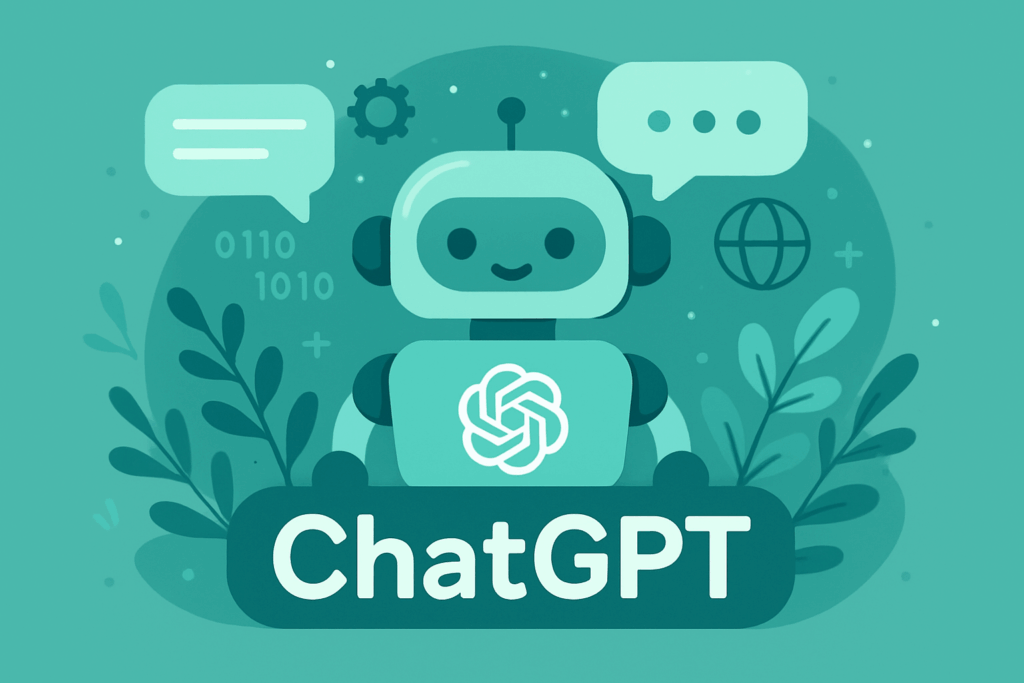
AIを活用した競合調査の最前線:ChatGPTで差をつける!
しかし近年では、ChatGPTをはじめとする生成AIの活用により、短時間で精度の高い競合分析が可能になってきています。
このセクションでは、実務に応用できるAIの活用方法やプロンプト例を紹介しながら、AIによる競合調査の最前線を解説します。
ChatGPTを使った競合調査の基本プロンプト例
生成AIは、質問の仕方=プロンプトによって得られるアウトプットの質が大きく変わります。以下は競合調査で実際に使えるプロンプト例です。
競合サイトの要点整理
「https://example.com」のWebサイトを分析し、サービス内容・強み・弱みを要約してください。
口コミ情報の分類
以下のレビュー内容をポジティブとネガティブに分類し、それぞれの傾向を3つずつ箇条書きしてください。→(レビュー本文)
業界全体の比較観点の洗い出し
○○業界における競合分析を行う際に見るべきポイントを10個挙げてください。価格、品質、サポート体制などを含めてください。
サービス比較表の生成依頼
A社・B社・C社の主要サービスを機能別に比較する表を作成してください。以下に3社の情報を記載します。
これらを応用すれば、競合サイトの構成・訴求ポイント・弱点などを自動で整理でき、初期分析の時短と網羅性向上に役立ちます。
AIで競合の強み・弱みを抽出する方法
ChatGPTはテキストの意味理解・構造整理に強みがあり、定性的情報から競合の特徴を抽出するのに適しています。
例えば競合企業の会社概要、プレスリリース、SNS投稿などを読み込ませることで
・商品力やブランディングの強み
・UXの未成熟な点や訴求の偏り
・顧客接点における改善余地
などを短時間で浮き彫りにできます。定性調査の補助として、非常に有効なツールです。
AIによる構造分析と視覚的整理
ChatGPTはテキストを「リスト」「テーブル」「階層構造」として出力することも可能です。
これにより、次のような視覚的アウトプットが可能になります。
・サービス内容の項目ごとの比較表
・サイト構造のツリー化
・商品特徴のマトリクス形式整理
例:
競合A:価格◎|カスタマーサポート△|スピード◯
競合B:価格△|カスタマーサポート◎|スピード△
自社:価格◯|カスタマーサポート◯|スピード◎
こうした形式に落とし込むことで、比較検討が容易になり、社内レポートや提案資料にも活用しやすくなります。
AI活用のメリットと限界
メリット
・情報収集・整理が短時間で可能になる
・定性的情報の構造化・仮説抽出が容易
・人的作業では見落としやすい比較視点を発見できる
注意点・限界
・リアルタイム性に弱い(特に無料版ChatGPTは最新情報未収録)
・事実確認が必要(生成内容に誤りが含まれることがある)
・解釈・判断は人間が行うべき(AIは「情報補助」)
AIの回答を盲信せず、「仮説の種」として活用することが重要です。ファクト確認と組み合わせることで、最も効果的に機能します。
競合他社の情報収集と評価方法
単にWebサイトを見るだけではなく、一次・二次調査の使い分けや、専用ツールの活用によって、効率的かつ多角的にデータを取得できます。
この章では、実務で役立つ情報収集の基本手法と評価方法、さらに分析ツールを活用する方法について解説します。
情報収集の手法
競合に関する情報は、主に以下の2つのアプローチで収集されます。
・一次調査(Primary Research):自社が独自に情報を集める方法
→ 例:インタビュー、アンケート、現地観察、ユーザーテストなど
・二次調査(Secondary Research):既に公開されている情報を活用する方法
→ 例:Webサイト、SNS、業界レポート、ニュース記事、特許情報など
一次調査は深く具体的な情報が得られる一方、コストと手間がかかります。二次調査は手軽かつ網羅性に優れますが、情報の鮮度や信頼性には注意が必要です。目的に応じて両者をバランスよく活用することが効果的です。
一次調査と二次調査の違いと使い分け
| 項目 | 一次調査 | 二次調査 |
|---|---|---|
|
情報の入手先 |
自社が独自に収集 |
他者が既に公開している情報 |
|
主な手段 |
インタビュー/アンケート/観察 |
Webサイト/報道/市場レポートなど |
|
メリット |
ニーズに合った深い情報を得られる |
手軽・スピーディー・コスト低 |
|
デメリット |
時間・コストがかかる |
情報が古い/自社に最適とは限らない |
たとえば、業界全体の傾向を把握する際は二次調査、特定ターゲット層の反応を探る場合は一次調査を使うと効果的です。
WebサイトやSNSを活用した競合動向の追跡
実務では、競合のWebサイトやSNSを定期的にチェックすることで、以下のような情報を得られます。
・商品ラインナップの更新
・価格変更やキャンペーンの実施状況
・ブランドメッセージの変化
・顧客とのエンゲージメント傾向(投稿頻度・反応など)
チェックポイント例:
・Webサイト:トップページ、料金表、FAQ、採用情報、ブログ
・SNS:投稿内容、コメント欄、フォロワー属性、ハッシュタグ
特に「Instagramで商品の使い方を発信している」「Xでクーポン配布している」といった動きは、戦略のヒントになります。
競合他社の評価基準
評価基準を明確にすることで、自社との比較が容易になり、戦略に活かせる実践的な示唆が得られます。
このセクションでは、競合の製品・サービス、価格戦略、市場シェア、マーケティング手法といった代表的な評価軸を紹介し、それぞれの分析ポイントを解説します。
製品・サービスの特徴と機能の比較
・主な機能・性能(例:スピード、操作性、拡張性)
・顧客ニーズとのマッチ度
・保証・サポート体制
・オンライン・オフラインでの提供形態
・顧客からの評価(レビュー・口コミ)
比較表を使って整理することで、客観的に差異を把握できます。
| 項目 | 競合A | 競合B | 自社 |
|---|---|---|---|
|
機能の豊富さ |
◎ 多機能だが複雑 |
△ 機能は少なめ |
◯ 必要機能に絞り操作性高い |
|
サポート体制 |
△ 平日昼間のみ |
◯ チャット対応あり |
◎ 電話・チャット・土日も対応 |
|
カスタマイズ性 |
◯ 一部可能 |
◎ 完全自由設計 |
△ テンプレート中心 |
こうした表を作ることで、自社の優位点と改善点を視覚的に整理でき、戦略に組み込むべきポイントが明確になります。
価格設定と市場シェアの分析
競合の価格戦略は、顧客獲得やブランディングに直結する重要な要素です。以下のような視点で分析を行います。
・価格帯と提供価値のバランス
例:高価格でも高機能/低価格でも満足度が高い、など
・課金モデル(買い切り・月額・成果報酬・フリーミアム)
・割引・キャンペーン戦略の有無
・価格に対する顧客の反応(レビュー・SNS)
あわせて、市場シェアのデータが取得できる場合は、どの価格帯が最も支持されているかも確認すると有益です。
例:
・競合A:高価格帯、シェア25%(BtoBに強い)
・競合B:中価格帯、シェア40%(個人・中小に人気)
・自社:低価格帯、シェア15%(新興だが伸び率高)
こうした情報をもとに、価格競争で勝つのか、それとも機能や価値訴求で勝負するのかを明確にできます。
マーケティング戦略の詳細な調査
マーケティング活動の評価では、以下のような観点を重視します。
・広告出稿の有無と媒体選定(Google広告、SNS広告、テレビCMなど)
・オウンドメディア運用状況(ブログ・メルマガ・動画など)
・SNS活用の度合い(投稿頻度、フォロワー数、反応率)
・ブランディング・メッセージの一貫性
・キャンペーン・イベントの仕掛け方
調査例:
・競合Aは「教育コンテンツ」で信頼構築 → ブログとYouTubeが主軸
・競合Bは「インフルエンサー連携」 → SNS広告・コラボ投稿が中心
これらを把握することで、「なぜ競合が選ばれているのか?」という本質的な理由に近づくことができ、自社の施策見直しに直結する示唆が得られます。

自社のポジションを明確化する
自社の強み・弱み、顧客構造、Webサイトの状況などを整理することで、市場におけるポジショニングが明確になり、競争優位の確立や改善施策の優先順位づけがしやすくなります。
このセクションでは、自社ポジションの明確化に必要なデータ分析や評価方法を解説します。
自社データの収集と整理
まず取り組むべきは、社内に点在しているデータを収集・体系化することです。具体的には以下のような情報を対象とします。
・顧客情報(年齢・性別・エリア・購入履歴など)
・営業・販売実績(売上推移、商品別構成比)
・Webサイト・LPのアクセスログ(Google Analytics等)
・問い合わせ履歴やクレーム内容(CRM・カスタマーサポート)
これらをGoogleスプレッドシートやBIツールで整理することで、戦略立案に使える“見える化”が進みます。
使用ツール例:
・Google Analytics(アクセス解析)
・Google Search Console(検索パフォーマンス)
・SalesforceやHubSpot(顧客管理とセグメント分析)
データが整理されていることで、後の分析や施策決定がスムーズになります。
顧客データの分析とセグメンテーション
次に重要なのが、顧客を意味のあるグループに分類(セグメント化)することです。代表的な手法には以下があります。
■ RFM分析(Recency・Frequency・Monetary)
・Recency:最後に購入したのはいつか?
・Frequency:どれくらいの頻度で購入しているか?
・Monetary:どれだけの金額を購入しているか?
RFMのスコアによって「ロイヤル顧客」「休眠顧客」などに分類でき、各層へのアプローチを最適化できます。
■ LTV分析(顧客生涯価値)
顧客1人が将来的にどれだけ利益を生むかを予測し、広告コストやサポート施策とのバランスを評価
■ デモグラフィック・行動分析
年齢・性別・地域・流入元などをもとにセグメント分けし、施策効果を最大化
このように、数字から「誰に何を届けるべきか」が見えてくることで、自社の戦略をより精密に設計できます。
自社製品・サービスの強みと弱みの特定
競合と比較するためには、自社が提供する価値の棚卸しも不可欠です。
評価ポイント:
・技術力や独自機能(例:UIの使いやすさ、他社にない設計)
・カスタマーサポート・対応スピード
・価格に対するコストパフォーマンス
・ブランドの認知・信頼性
・顧客からのフィードバック(NPSやレビュー)
分析例:
顧客から「電話がすぐつながる」と高評価 → サポート品質が差別化要素
逆に「デザインが古い」と言われる → UI改善が急務
このように、強みは伸ばす・弱みは補うという基本方針で、戦略を具体化できます。
自社WebサイトのSEOとトラフィック分析
オンラインでの競合力を測る上で、Webサイトの状況を分析することも重要です。以下の指標を確認しましょう。
・オーガニック検索流入(キーワードごとのCTRや掲載順位)
・離脱率・直帰率・平均滞在時間(UX改善のヒントに)
・コンバージョン率(資料請求・購入・問い合わせ)
・モバイル対応や表示速度(技術面での足かせ有無)
ツール例:
・Google Analytics(トラフィック・ユーザー属性分析)
・Google Search Console(検索キーワードと順位把握)
・PageSpeed Insights(サイトスピード評価)
これらを使い、「競合より検索流入が弱い」「CV率は高いがセッション数が少ない」といったボトルネックを発見し、具体的な改善施策に落とし込みます。
市場分析とトレンドの把握
特に近年は、技術革新や消費行動の変化が急速に進んでおり、環境の変化に対応できる柔軟な視点が求められます。
このセクションでは、外部環境を捉えるPEST分析、市場トレンドへの対応方法、新規参入や業界構造の変化に対する戦略的なアプローチについて解説します。
PEST分析で外部環境を評価する
| 要素 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
|
Political(政治) |
政府の規制・税制・貿易政策など |
広告業界における景品表示法の強化、補助金制度の変更 |
|
Economic(経済) |
景気、為替、金利、インフレなど |
消費者の可処分所得の減少、物価高による購買意欲の低下 |
|
Social(社会) |
価値観、人口構成、ライフスタイルなど |
SDGs意識の高まり、若年層の消費スタイルの変化 |
|
Technological(技術) |
テクノロジーの進化、新サービスの登場 |
AI、IoT、生成系AI(ChatGPTなど)の普及による業務変革 |
PEST分析の目的は、リスクの早期察知だけでなく、トレンドに先回りした機会の発見にもあります。たとえば、生成AIの登場によってWeb制作やマーケティングのプロセスが大きく変わるといった構造的変化は、競争優位性の再構築のチャンスにもなります。
市場トレンドの変化に対応する方法
市場のトレンドを的確に捉えることは、競争に勝ち残るための重要な要素です。以下のようなアプローチで変化に対応する組織体制と行動を設計します。
■ トレンドの識別方法
・定期的な業界ニュースチェック(PRTIMES、日経クロストレンドなど)
・GoogleトレンドやSNS分析を使ったキーワード変化の観察
・既存顧客の要望・クレーム・レビューの内容変化
■ 対応アクション例
・トレンドに合致した新サービスの投入(例:サブスク型プラン導入)
・UI/UXのトレンド(フラットデザイン、AIチャット対応など)を踏まえた改修
・コンテンツの再設計(ブログや動画の構成・発信タイミングの見直し)
変化を見逃さず、早期に打ち手を講じることで、競合に先んじて市場ポジションを獲得できます。
新規参入者や業界変化への対応策
市場構造が変化する中で、新たな競合プレイヤーの出現や業界再編といった事象が自社のシェアに大きな影響を及ぼします。以下の対応策を通じて、柔軟かつ戦略的に備える必要があります。
■ 競合出現時の分析ポイント
・どの顧客層をターゲットにしているか
・価格・サービス・チャネルなどでの差別化点
・広告出稿やSNS活動の積極性
■ 業界再編時の対応戦略
・ポジショニングの再構築(例:特化型→総合型へ転換)
・パートナーシップの強化(例:連携サービスで付加価値提供)
・内製化・外注化の見直しによるスピード強化
■ ケーススタディ(提案事例)
ある中小SaaS企業は、大手の市場参入により価格競争に巻き込まれたが、逆に「低価格すぎない・カスタマーサクセス重視」のニッチ戦略に転換し、定着率とLTVを向上させた。
このように、環境変化は脅威にも機会にもなりうるため、柔軟なリスクマネジメントとポジショニング戦略が鍵となります。
戦略立案と具体的な施策の策定
ここでは、現状のポジショニングを見直し、強みを活かす戦略を設計し、実行可能な施策に落とし込む方法について解説します。
戦略と施策が一貫していなければ、せっかくの分析も効果を発揮しません。重要なのは、戦略を「行動」へと具体化するプロセスです。
自社の強みを活かした差別化戦略の構築
競合が増え、価格や機能での差別化が難しくなっている今こそ、「自社ならでは」の価値を見直すことが重要です。差別化戦略を設計する際には、以下の3つの視点を意識しましょう。
■ 1. 顧客視点の強み分析
・過去の商談やクチコミ、レビューから「選ばれた理由」を抽出する
・LTVが高い顧客の傾向を分析し、どんな価値に対価を払っているかを把握
■ 2. 競合比較によるポジショニングの明確化
・機能、価格、導入スピード、サポート体制などの観点で比較表を作成
・あえて「尖った特徴」に集中し、すべてを平均点にしない勇気も必要
■ 3. 社内リソースに即した戦略の現実性
・実現可能な範囲で強みを発揮できる分野を選定
・小さな市場でも圧倒的シェアを取る“ドミナント戦略”も有効
実行可能なアクションプランの設計
戦略が明確になったら、次は具体的な「施策」へと分解します。下記のステップでアクションプランを構築しましょう。
■ ステップ1:目的の明確化
「市場シェアを3か月で5%上げる」「CV数を月30件にする」など、数値目標を明確に設定。
■ ステップ2:KPIとKGIの分解
・KGI:月間30件のCV獲得
・KPI:LPのCTR改善、広告流入増加、CTAのクリック率向上
■ ステップ3:チャネル別戦略
| チャネル | 施策例 |
|---|---|
|
Web広告 |
競合他社の出稿傾向に合わせたリスティング強化 |
|
SEO |
競合が取りこぼしているニッチキーワードで記事投入 |
|
SNS |
他社比較投稿やユーザー生成コンテンツを活用 |
|
セミナー・展示会 |
比較資料の無料配布で見込み客を獲得 |
■ ステップ4:実行担当・スケジュール化
施策ごとに担当と期日を設定し、進捗を可視化。
→NotionやGoogleスプレッドシートで管理するテンプレート例も活用可能です。
成果検証と改善のPDCAサイクル
施策の実行後は必ず結果を計測し、次の施策へとつなげる「改善」のサイクルを組み込みましょう。
■ 評価指標の例
・広告CVR、LP離脱率、競合との価格比較によるCV差異
・顧客の流入経路、成約理由のアンケート調査
■ 改善アクションの例
・問い合わせ率が低いLPの見出しとCTAをABテストで検証
・競合が強化している領域に対し、あえて別軸で訴求(例:価格→安心感)
施策のPDCAを高速で回すことで、競合よりも先に“勝ちパターン”を確立できます。
成果最大化に向けた継続的改善とAI活用
現代のビジネス環境では、継続的に市場の動きをモニタリングし、戦略を柔軟に見直すことが成果最大化の鍵となります。
ここでは、持続的な競合分析と改善活動の重要性、そしてAIを活用した効率化の方法について紹介します。
データの定期チェックと戦略の見直し
戦略の効果は時間とともに変化します。以下のようなタイミングで、競合分析と戦略の見直しを行うのが効果的です。
■ 定期的な見直しの推奨頻度
・月次:広告効果やサイト分析(例:Googleアナリティクス)
・四半期:市場動向や競合のサービス改定状況
・半期〜年次:自社の中期計画や価格戦略の妥当性評価
■ 見直しのポイント
・競合が新たに開始したキャンペーンや提携の有無
・自社のKPI進捗とギャップ分析
・顧客からのフィードバックやSNSでの反応
ChatGPTを活用した継続的分析の実践例
AIツール、とくにChatGPTのような生成AIは、情報整理・仮説立て・施策検討を効率化する強力な味方です。
■ 実用プロンプト例(ChatGPT活用)
| 使用シーン | プロンプト例 |
|---|---|
|
競合比較 |
「○○業界の主要3社の強み・弱みを整理して」 |
|
自社戦略の壁打ち |
「○○の強みを活かした新しい訴求方法を提案して」 |
|
コンテンツ設計 |
「△△に興味がある顧客向けのブログネタを10個出して」 |
|
施策レビュー |
「このKPIが改善しない理由と対策を考えて」 |
■ 継続活用のコツ
・定期レポート作成のサポート(例:月次レポートの要約)
・チーム内アイデア出し会議でのたたき台生成
・仮説ベースの施策設計(例:「この広告が響かない理由」など)
AIをパートナーとして活用することで、属人的になりやすい競合分析も、再現性とスピードを両立できます。
成功を持続させる組織文化の醸成
分析と改善を形骸化させないためには、組織として「考え続ける」文化を育てる必要があります。
■ 継続改善のための仕組みづくり
・月次で競合情報・数値結果を共有する「報告会」の実施
・営業・マーケ・企画チームが横断的に参加する「競合検討会議」
・KPI未達時の“責任追及”ではなく、“仮説と改善”を促す評価制度
AIやツールはあくまで支援手段です。重要なのは、それを活用する「人」と「組織」の姿勢。継続的な改善文化が根付けば、市場変化に柔軟に対応し、競合優位を長く維持できます。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。