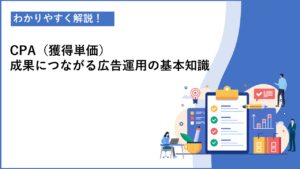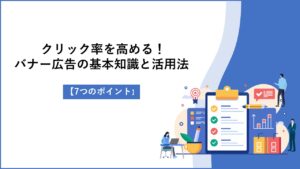WEB広告基本
WEB TANOMOOO
【対策まとめ】CPA高騰の真相と今すぐできる改善策5選
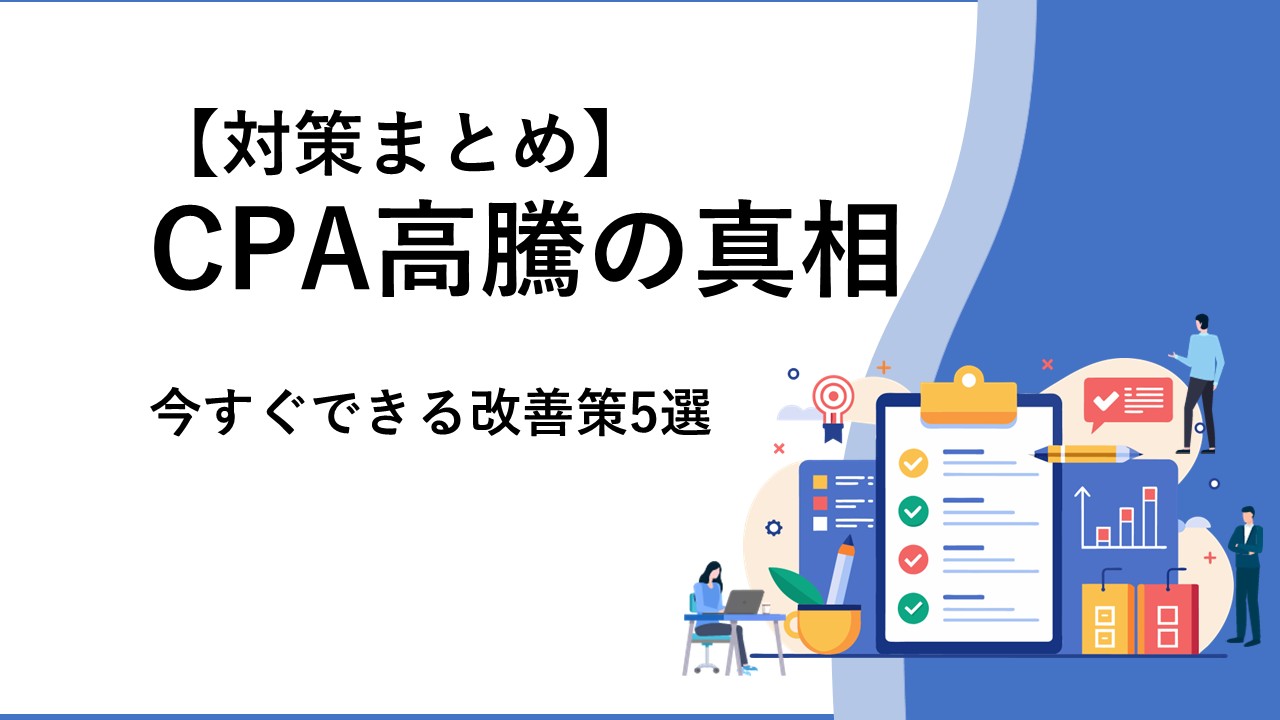
CPA高騰の背景と原因を徹底解説
この章では、そもそもCPAとは何か、広告運用にどのような影響を及ぼすのか、また「目標CPA」との関係性についてわかりやすく解説します。
CPAという言葉は知っていても、正確な意味や改善の考え方まで理解している人は意外と少ないため、基本から丁寧に押さえておきましょう。
CPAとは?広告運用における重要指標
CPAとは「Cost Per Acquisition」の略で、1件の成果(コンバージョン)を獲得するためにかかった広告費を示します。
具体的には「広告費 ÷ コンバージョン数」で求められます。たとえば10万円の広告費で100件の資料請求があった場合、CPAは1,000円です。
この指標は広告施策の「費用対効果」を判断するうえで欠かせないものです。
成果が同じでもCPAが高くなれば、広告コストの負担が大きくなり、利益が減少します。だからこそ、CPAの管理と改善は広告運用の最重要課題なのです。
CPAが広告費用に与える影響
CPAが上昇すると、広告から得られるリターンが悪化します。
例えば、商品1件の利益が5,000円だったとしても、CPAが6,000円になれば1件ごとに赤字です。こうなると、広告運用は継続できなくなります。
さらに、CPAが高いまま広告を配信し続けると、予算消化が早まり、肝心のターゲットに十分アプローチできない状態に陥ります。
広告費をどれだけかけても成果が得られない「悪循環」に陥るリスクがあるため、CPAの高騰は早期に手を打つ必要があります。
CPAと目標CPAの関係性
「目標CPA」とは、広告運用において許容できる最大の獲得単価のことです。
たとえば、1件の資料請求で平均5,000円の売上がある場合、利益や固定費を考慮して「目標CPAは3,000円以下」と設定することがあります。
この目標値を上回るCPAが続くと、広告の費用対効果が合わなくなり、運用の見直しが求められます。
目標CPAは企業ごとに異なり、利益率・商材単価・成約率などをもとに設計されるため、適切に設定・管理することが重要です。
CPA高騰の主な原因
中でも重要なのは「CVR(コンバージョン率)の低下」と「CPC(クリック単価)の上昇」です。これらは直接CPAを押し上げる要素であり、広告運用で真っ先に見直すべきポイントです。
また、これらに加えて見落とされがちな「運用体制」や「配信戦略のズレ」なども原因になります。この章では、CPAが悪化する3つの典型的な要因を詳しく見ていきましょう。
CVR(コンバージョン率)の低下要因
CVRが下がると、クリック数が増えても成果が増えず、結果としてCPAが高くなります。
原因としては以下のようなケースが考えられます。
・ランディングページの内容と広告文にズレがある
・ページの読み込みが遅く、離脱が多発している
・フォーム項目が多すぎて完了率が低い
・ユーザーのニーズにマッチしていない訴求をしている
たとえば、注文住宅の資料請求ページで「費用の比較資料がもらえる」と広告に記載しているのに、実際のLPでは施工事例ばかりが並んでいた場合、ユーザーは「想像と違う」と感じて離脱してしまいます。
広告からLPまでの一貫性と、ユーザーにとって行動しやすい構成にできているかが、CVR改善の鍵になります。
CPC(クリック単価)の上昇要因
CVRやCPC以外にも、CPAを押し上げる見逃せない要因があります。
・シーズナリティの変化:例えば、注文住宅は春〜夏が繁忙期。時期によってCVが落ちやすくなります。
・ターゲットのずれ:想定しているペルソナと実際の配信先にギャップがあると、CVに結びつかないクリックが増えます。
・広告配信の最適化不足:配信学習が進んでいなかったり、除外設定が不十分だったりすると、成果につながりにくいユーザーに予算が浪費されてしまいます。
これらは一見気づきにくい要素ですが、CPA悪化の背景を探る際に必ずチェックすべきポイントです。特に、長期で運用しているキャンペーンほど、設定の陳腐化が起きやすいため、定期的な見直しが必要です。
CPA改善のための基本戦略
ここでは、成果を生みやすくする3つの基本施策「CVR改善」「LP最適化」「リマーケティング活用」について解説します。どれも即効性と中長期的な安定成果につながる対策です。
CVRを向上させる方法
CVR(コンバージョン率)を上げるには、ユーザーの行動心理に沿った導線設計が重要です。
・広告文とランディングページの訴求が一致しているか
・ファーストビューで「何が得られるか」が明確になっているか
・ボタンやフォームが目立つ位置に配置されているか
・不安を払拭する要素(口コミ・実績・保証など)があるか
たとえば「資料請求で家づくりの全体像がわかる」と訴求した広告には、資料の中身を一部見せる画像や、活用シーンの紹介を加えるとCVRが上がりやすくなります。
ランディングページの最適化
ランディングページ(LP)はCVRを左右する最重要要素です。
広告の品質スコアにも影響するため、最適化はCPA改善に直結します。
・表現やビジュアルが古くないか(見た目の第一印象)
・ページの読み込み速度が遅くないか(特にスマホ)
・情報の順序が「悩み→解決策→行動喚起」となっているか
・お問い合わせ・資料請求のハードルが高すぎないか
CVポイントを明確にし、複数のパターンでA/Bテストを実施することで改善ポイントを可視化できます。特にファーストビューとCTA(行動喚起)の位置と文言はテスト効果が出やすい部分です。
リマーケティングの活用
一度サイトを訪れたユーザーに対して再アプローチする「リマーケティング」は、CPAを効率よく改善する強力な手段です。
・商品やサービスに興味はあるが、今すぐ行動しない層に再訴求できる
・LPの改善やCPC削減が難しい時も、リマケで補填できる
・滞在時間や訪問ページに応じた「セグメント配信」で反応率が向上する
例)住宅購入検討者が「価格比較ページ」まで見て離脱した場合、再訪問を促すバナーに「月々の支払い例付き資料がもらえる」と訴求すれば、興味を具体的に刺激できます。
CPCを抑える方法
CPA(顧客獲得単価)を改善するには、CVRの向上に加えてCPC(クリック単価)を下げる施策も重要です。クリックされるたびにコストが発生する以上、CPCが高すぎると効率が悪く、獲得単価が上がってしまいます。
ここでは、主に以下の3つの軸でCPCを抑える方法を解説します。
品質スコアの改善
Google広告などでは、広告の「品質スコア(広告の関連性・CTR・LPの利便性)」が高いほど、低いCPCで広告を上位表示できる仕組みになっています。
品質スコアを改善するには
・広告文とキーワード、LPの内容を一致させる
・クリック率(CTR)を高めるためのタイトル改善や訴求の明確化
・モバイルユーザー向けに表示スピードを最適化する
たとえば「土地探し 相談無料」のキーワードであれば、広告文やLPでも「無料相談」にフォーカスした内容に統一することで、品質スコアが高まりやすくなります。
キーワード選定の見直し
キーワードの選定によっては、競争が激しくCPCが高騰しているワードを無意識に使っている場合があります。
・高CPCキーワードをレポートで洗い出して除外する
・「資料請求 無料」「家づくり 相談」などのロングテールキーワードに変更する
・あいまいな単語(例:「住宅」「リフォーム」)は除外キーワード設定で無駄クリックを防ぐ
CPA改善では「とにかく検索数の多いワードを狙う」よりも、費用対効果の高いニッチワードで確実に獲得する設計が求められます。
自動入札戦略の活用
Google広告やYahoo!広告には、目的に合わせてCPCを自動で最適化する「自動入札戦略」が用意されています。
・「目標コンバージョン単価(tCPA)」で、CPAを一定水準に保つ
・「コンバージョン数の最大化」で、限られた予算内で最大効果を狙う
・機械学習による自動調整で、競合が多い時間帯の無駄な高騰を防止
手動でCPCを細かく管理するよりも、適切な戦略を選んで任せる方が成果につながるケースが増えています。
広告クリエイティブの改善
どれだけターゲティングや入札戦略を工夫しても、広告自体に魅力がなければクリックにもつながりません。ここでは、CPAを下げるための具体的なクリエイティブ改善手法を紹介します。
ユーザー心理に基づいた訴求ポイントの強化
広告文や画像は、単に商品・サービスの機能を並べるだけではユーザーの心に響きません。ユーザーの課題や欲求に共感する訴求が必要です。
ポイント:
・「ベネフィット訴求」:例)×「自動車保険の比較サイト」→○「5分で月3,000円安くなる保険が見つかる」
・「緊急性の提示」:例)「今週末までの期間限定」「残り5枠」
なぜ有効か:
・ユーザーは“商品そのもの”より“自分にどう役立つか”に反応します。
・ベネフィット型コピーはCTR(クリック率)とCVRを同時に向上させる効果が高く、CPAの改善にもつながります。
フリークエンシーキャップの設定で広告疲れを防止
同じ広告が短期間で何度も表示されると、ユーザーは「見飽きた」「うっとうしい」と感じ、クリック率や印象の質が低下します。この現象を「広告疲れ(Ad Fatigue)」と呼びます。
対策:
・フリークエンシーキャップ(1ユーザーあたりの表示上限)を設定し、1日2~3回までなどの制限を設ける。
・GoogleやMeta(Facebook)広告では、キャンペーン単位で設定が可能です。
実務上の効果:
・過剰配信を防ぐことで無駄なインプレッションを減らし、CPC(クリック単価)の無駄遣いを回避。
・フレッシュなユーザーに届けやすくなり、CPA改善に寄与。
定期的なクリエイティブの更新
クリエイティブの効果は時間と共に薄れます。特に同一ターゲット層に継続配信している場合、一定期間後にはCTR・CVRが目に見えて低下する傾向があります。
実践アクション:
・「月1〜2回の頻度で、新しい訴求軸・デザインをテストする。
・同じコンセプトでも画像・色・フォント・コピーなどの要素を変えるだけでCTRが改善する場合も。
補足:
・A/Bテストやマルチバリエーション配信を活用し、実データで勝ちクリエイティブを見つける運用が効果的です。
・動的クリエイティブ(DCO)を使えば、自動で最適化された組み合わせを配信可能です。
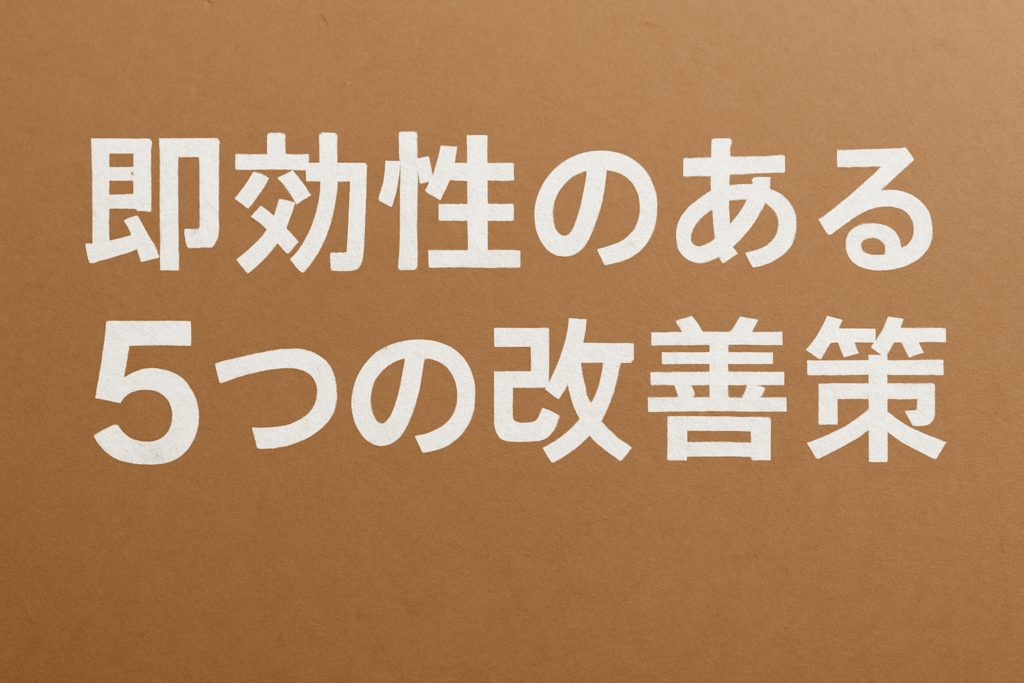
即効性のある5つの改善策
改善策1:ターゲティング設定の再構築
精緻なターゲティングで関連性を向上
闇雲にターゲットを広げるのではなく、過去の成果データや顧客像をもとに精度を高める必要があります。
実践例:
・Google広告 → オーディエンスセグメント(アフィニティ・カスタムインテント)を細分化。
・Meta広告 → 類似オーディエンスではなく、既存顧客ベースの精密カスタムオーディエンスへ再設定。
地域や年齢、性別といった基本属性も、実績の高い条件だけに絞ることで効率化。
ターゲット層に合わせた広告配信
精度の高いターゲティングを行っても、訴求がズレていれば成果には結びつきません。ユーザーのニーズや関心に合ったメッセージを届けることが不可欠です。
改善施策:
・ペルソナごとに広告文・画像を出し分ける(例:20代女性向け/30代子育て世代向け)
・LPの内容と広告訴求を連動させることで、「期待と結果のズレ(期待ギャップ)」を解消
・「成果が出ていない配信グループ」を停止 or 除外し、配信効率を最大化
改善策2:ランディングページの最適化
コンバージョンを促進するデザインとコピー
「誰に、何を、なぜ、今すぐ」行動してもらいたいのか――その意図が伝わらなければCVRは上がりません。
主な改善ポイント:
・ファーストビューに強い訴求+ベネフィット+CTA(行動喚起)を集約
・スマホ表示を重視したスクロールしやすい構造
・CTAボタンの設置位置・文言の最適化(例:「無料で資料請求する」など明確な動機付け)
・信頼性(実績・レビュー・導入事例)を視覚的に示すセクションを設置
ページ読み込み速度の改善
表示が遅いだけでユーザーはページを離れます。とくにスマートフォン環境では数秒の遅延が大きなCVR低下を引き起こします。
チェックすべき項目:
・画像サイズの圧縮(WebP形式などへの変換)
・不要なスクリプトやタグの削除
・Googleの PageSpeed Insights で速度スコアを確認し、モバイル最適化を重点的に改善
A/Bテストによる効果測定
「改善したつもり」が成果に結びつくとは限りません。デザインや文言の変更は、検証を伴って初めて意味を持ちます。
実行のステップ:
・CTAボタンの文言変更(例:「今すぐ無料相談」vs「資料をダウンロード」)
・ファーストビューのキャッチコピー比較
・LP内の構成順(導入事例の位置、料金表示のタイミングなど)
1つずつ仮説→実施→検証→改善というプロセスを回すことで、継続的にCVRの改善が期待できます。
改善策3:キーワード戦略の見直し
競争の激しいキーワードの除外
CPCが高騰しているキーワードに無理に入札し続けると、予算消化が早く、CPAも高止まりしやすくなります。
対処方法:
・過去の配信結果から費用対効果の悪いキーワードを洗い出す
・競合が多く入札単価の高いビッグワード(例:「住宅ローン」「ダイエット」など)を見直し
・完全一致やフレーズ一致に変更し、意図しない検索への表示を防ぐ
「表示回数が多い=成果が出る」ではないため、成果につながりやすい意図の明確な検索語句に絞り込みましょう。
ロングテールキーワードの活用
競争が激しくないが、ニーズが明確な検索語句(ロングテール)は、CVRが高くCPAの改善につながりやすい傾向があります。
活用のポイント:
・地域名や年齢、用途を加えた具体的なキーワード例:「渋谷 賃貸 ファミリー向け」「30代女性向け スキンケア」
・Google検索語句レポートをもとに、成果につながった検索語句から逆算
LPや広告文もロングテールに合わせて設計すると、関連性が高まり品質スコアも向上
重複キーワードの整理
似た意味を持つキーワードや同義語が複数登録されていると、内部競合を起こし、配信効率が低下します。
対策手順:
・キーワード一覧を精査し、類似語・表記揺れの統一
・パフォーマンスの高いキーワードを軸にグルーピングと整理
・否定キーワード設定を活用し、無駄な表示やクリックをブロック
キーワード管理の精度を高めることで、意図したユーザーにだけ広告が届き、CPAを抑える土台が整います。
改善策4:広告クリエイティブの刷新
ユーザーの興味を引くビジュアルとコピー
現代のユーザーは大量の広告にさらされており、一瞬で目を引くクリエイティブでなければスルーされがちです。
具体的な改善ポイント:
・ターゲット層の悩みや欲求を冒頭のコピーに反映
・商品やサービスのビフォーアフターを視覚的に表現
・写真・動画はプロ品質のものを使用し、印象に残る演出を加える
例)「たった5分で変わる肌質」や「3ヶ月で−10kg達成」など、メリットが明確で信頼感のある訴求が効果的です。
動画広告の活用でエンゲージメント向上
動画広告は静止画やテキストに比べて情報量が多く、ユーザーとの接触時間も長くなるため、エンゲージメントの高い施策です。
活用のポイント:
・最初の3秒で「興味を引く」構成(フック)を設計
・ターゲットが抱える課題 → 解決策 → 利用後のイメージをストーリーに
・短尺動画(15秒前後)と縦型フォーマットでSNSに最適化
特にSNSやYouTube向けでは、視覚と音声の両方で訴求できるため、高い成果が期待できます。
定期的なクリエイティブの更新で広告疲れを防止
同じ広告を長期間配信していると、ユーザーは見慣れてしまい反応が鈍くなります。これがいわゆる「広告疲れ(Ad fatigue)」です。
更新タイミングと運用例:
・2〜4週間ごとに新しいバリエーションを投入
・同一商品の場合も、切り口やコピーを変えた複数パターンをABテスト
・配信結果をもとにクリック率・CVRの高いクリエイティブに絞る
効果的なクリエイティブ更新の習慣を持つことで、安定的な成果と低CPAを維持できます。
改善策5:広告運用の自動化
Google広告の自動入札戦略の活用
Google広告では、コンバージョン数最大化や目標CPAなどに基づいた自動入札が可能です。
活用のポイント:
・「目標CPA」入札:一定のCPAを維持したい場合に有効
・「コンバージョン数の最大化」:短期間でCVを増やしたいときに効果的
・過去の配信データをもとに、AIが自動で最適な入札を調整
人の手では難しいリアルタイムの最適化が可能となり、手間をかけずにCPAを抑えることができます。
広告予算の効率的な配分
自動化ツールでは、費用対効果が高い広告グループやキーワードに予算を集中させることも容易です。
実践例:
・パフォーマンスの高いキャンペーンに自動で多くの予算を振り分け
・成果の出にくいターゲットや時間帯には配信を抑制
・「予算配分の最適化」をオンにして全体の広告効率を最大化
これにより、無駄な広告費を削減し、CPAの改善にも直結します。
定期的な効果測定と運用改善
自動化とはいえ、完全に放置すれば成果は鈍化します。データを定期的に確認し、自動化ツールの挙動を把握することが重要です。
継続的改善の流れ:
1.月次レポートでCPAの推移やコンバージョン率を確認
2.広告グループ単位で成果の良し悪しを分析
3.自動入札やターゲティングを見直すタイミングを設定
「自動化 × 定期的なレビュー」のハイブリッド運用が、継続的なCPA改善と成果安定化の鍵になります。

効果的な広告運用のための継続的な取り組み
定期的なデータ分析と改善
広告運用では、データに基づく改善サイクル(PDCA)を回すことが基本中の基本です。
実施ポイント:
・週次・月次でCPA・CVR・CPCなどの指標を確認
・配信データからターゲットや配信時間帯の傾向を分析
・パフォーマンスが悪化している要因を特定し、早期に対策
「感覚」ではなくデータドリブンな運用を心がけることで、費用対効果の改善につながります。
広告媒体ごとの効果測定
広告媒体ごとにユーザー層や特性が異なるため、一律の評価軸で比較しても正確な判断はできません。
具体的な取り組み:
・Google広告は検索意図の強いユーザー向け
・Facebook広告やInstagram広告は興味喚起や認知拡大が得意
・各媒体の目的別にKPI(成果指標)を明確化
成果が出ている媒体に予算を再配分する戦略判断も、CPA最適化には欠かせません。
インプレッションシェアの確認
「どれだけの潜在ユーザーにリーチできているか」を示すインプレッションシェア(表示回数のシェア)も重要な指標です。
注意点と活用法:
・シェアが低い場合は入札単価や広告ランクの見直しが必要
・表示されていてもクリック率が低ければ、クリエイティブや訴求に問題
CPAだけでなく、表示の機会そのものに目を向けることで、新たな改善ポイントを発見できます。
チーム内での運用体制の強化
特に複数の媒体を運用する場合や、運用が長期化する場合には、属人的にならず、チーム全体で改善の視点を持つことが重要です。
広告運用担当者のスキル向上
広告運用の成果は、担当者の知識と経験に依存する割合が大きいのが実情です。媒体アップデートも頻繁なため、継続的な学習が不可欠です。
実施ポイント:
・各媒体の公式トレーニングや認定資格の取得
・最新の広告トレンドやAI活用事例のキャッチアップ
・自社実績の分析によるナレッジの蓄積と反映
スキル向上によって、新しい機能を活用した戦略的な運用が可能になります。
運用型広告の専門知識の共有
広告運用は、担当者1人に依存するとリスクが高まります。
属人化を避けるため、知識や判断基準をチーム全体で共有する文化をつくることが必要です。
具体的な取り組み:
・月1回の運用報告会や共有会の実施
・成功・失敗事例をドキュメント化して蓄積
・外部パートナーとの情報交換による相互学習
こうしたナレッジ共有が、トラブル対応力の向上や新人育成の効率化にもつながります。
効果的な広告施策のPDCAサイクルの実践
成果を上げているチームには、必ずPDCA(Plan→Do→Check→Act)を定着させる運用文化があります。
実行例:
・Plan:KPI設定と仮説立て
・Do:配信設定と実行
・Check:月次レポートで検証
・Act:改善施策の実施と再設計
このサイクルをチーム全体で継続して回すことで、CPA改善の成功確率が大幅に向上します。
最新トレンドの取り入れ
特に昨今のWeb広告業界では、AI活用や動画広告、インタラクティブ広告の普及など、日々新しいトレンドが登場しています。
これらを積極的にテスト・導入することが、競合他社との差別化やCPA削減の鍵になります。
Meta広告の活用
Meta広告(旧Facebook広告)は、精緻なターゲティングと柔軟なクリエイティブ配信が強みです。特に不動産・美容・教育業界などでは、属性に合わせた見込み顧客の絞り込みが可能で、成果につながりやすい傾向にあります。
活用ポイント:
・InstagramとFacebook両方を自動配信でカバー
・リード広告でCVRの高いユーザーを獲得
・オーディエンス拡張機能(類似ユーザー)によるCPAの安定化
競合がGoogle広告に集中している場合、差別化を図るチャンスにもなります。
動画広告やインタラクティブ広告の導入
静止画やテキストだけでは伝えにくい訴求内容を、動画広告が効果的にカバーできます。YouTubeはもちろん、TikTokやInstagramリールなど、短尺動画に強いプラットフォームも注目されています。
また、最近ではインタラクティブ広告(ユーザー参加型広告)も注目されており、エンゲージメントが高く、クリック以外の指標でも広告効果を最大化できる可能性があります。
活用例:
・アンケート型広告でユーザーの意識変化を促進
・動画を活用して商品理解や信頼獲得を向上
・インストリーム広告とスキッパブル広告の使い分け
適切な導入で、CVR向上やCPC削減によるCPA改善が期待できます。
新しい広告媒体のテスト運用
主要媒体だけでなく、新興の広告媒体やニッチなプラットフォームのテストも効果的です。
たとえば、音声配信プラットフォームやアプリ内広告、位置情報広告など、ターゲットとの接点を拡張する施策は、まだ競争が激しくない分CPAが抑えられる傾向にあります。
実施例:
・LINE広告による属性ターゲティング
・スマホゲームアプリ内広告でのリーチ拡大
・SpotifyやVoicyなど音声メディア広告のテスト配信
定期的に新媒体をテストすることで、CPA効率のよいチャネルを見極める判断材料が増えます。
CPA改善のために今すぐ取り組むべきこと
しかし、重要なのは「すぐに手を打てる施策を見極め、着実に改善に着手すること」です。
このセクションでは、即時性と実行性のある対応策に焦点を当て、優先順位を明確にしながら、広告効果を最大化するためのアクションを提示します。
CPA改善の優先順位を明確化
まず最初に行うべきは、どの要素がCPA悪化の原因になっているかの特定です。広告成果に影響を与えるのは、CVR(コンバージョン率)、CPC(クリック単価)、ターゲティング精度、ランディングページ、広告クリエイティブなど多岐に渡ります。
優先順位の付け方:
・CVRが低下している ⇒ LPやフォームの見直しを最優先
・CPCが急上昇 ⇒ 入札戦略・キーワードの見直しを優先
・クリックはあるが成果につながらない ⇒ ターゲティングまたは訴求メッセージの調整が必要
このように、原因と対応策を正確に紐付けて優先度をつけることで、最短距離でのCPA改善が可能になります。
継続的な改善で広告効果を最大化
短期的な施策でCPAを下げられても、放置すればすぐに逆戻りするリスクがあります。広告運用は一度の改善で完了するものではなく、定期的なチューニングとテストが不可欠です。
継続的な取り組み例:
・毎週の指標チェック(CPC・CVR・CPA・CTRなど)
・月1回のABテスト結果の分析と施策更新
・媒体のトレンド情報を活かした訴求調整
こうしたルーティンを運用に組み込むことで、改善効果を定着させ、持続的なCPAコントロールが実現します。
効果的な広告運用で目標CPAを達成する
最終的なゴールは、「目標とするCPA水準で安定的に成果を出すこと」です。単にCPAを下げるだけでなく、リードの質や売上への貢献度まで含めたKPI設計と運用が重要です。
成果を最大化する考え方:
- CPAだけでなく、LTV(顧客生涯価値)やCV後の歩留まりも考慮
- チーム内で目標と実績の定期共有
- BIツールや広告レポートを活用した可視化と意思決定
広告運用は「費用対効果の最適化」が本質です。CPAの数字に一喜一憂するのではなく、マーケティング全体の成果を俯瞰した運用が、長期的な改善と成長に繋がります。
CPA高騰には構造的な対策と即効性のある改善を
CPA高騰は複数要因が絡む複雑な現象
そのため、「とりあえず入札単価を下げる」といった場当たり的な対処では、根本的な解決にはつながりません。
重要なのは構造的かつ段階的な改善アプローチ
CVRの向上、CPCの抑制、広告クリエイティブの刷新、ランディングページ最適化など、構造的にボトルネックを取り除くアプローチを段階的に進めることで、安定的かつ持続可能なCPA改善が実現できます。
即効性のある改善策で早期に成果を出しつつ、継続的改善へ
一方で、成果を持続させるためには、中長期視点でのPDCA運用、チーム体制の強化、新たな媒体や広告フォーマットのテスト導入なども欠かせません。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。