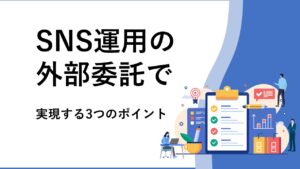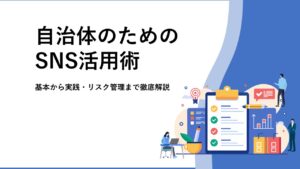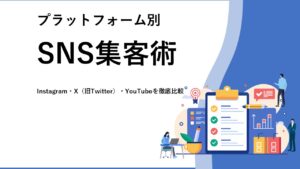SNS運用
WEB TANOMOOO
市民とのつながりを強化するSNS運用術|自治体広報の完全ガイド
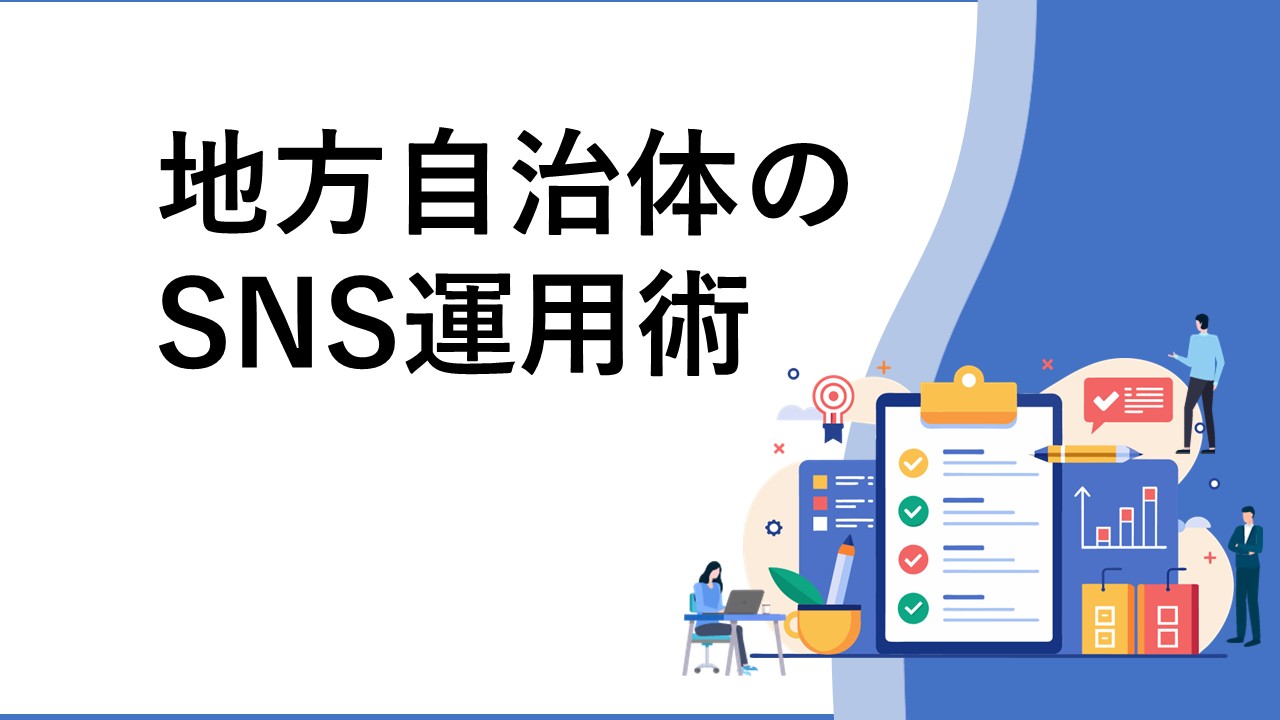
市民参加型SNS運用の意義と前提
投稿や告知だけでなく、市民の声(コメント、DM、アンケート、リアクション)を計画的に受け取り、意思決定やサービス改善に反映することで、情報の透明性が高まり、信頼と参加意欲が循環的に強化されます。
とくに広報担当に求められるのは、
①意図の明確化(誰に・何を・なぜ伝えるか)
②対話設計(どの接点で・どのように受け取り可視化するか)
③改善プロセス(定期的な検証と反映)
の3点です。
さらに、緊急時の即時性・平時の生活情報の利便性・地域の魅力発信によるシビックプライドの醸成といった目的が同居するため、KPI(重要業績評価指標)も「安全・利便・関与」の3系統で設計し、運用リソースに応じて優先順位を明確にしておくことが実務上の前提となります。
SNSが行政広報にもたらす価値(双方向性・即時性・到達性)
①双方向性:市民の反応が即時に取得でき、意思疎通が往復で成立すること、
②即時性:災害・事故・気象・交通など時間要素の大きい情報を迅速に届けられること、
③到達性:住民属性や関心に合わせて幅広く、あるいは絞り込んで届けられること、
の3点に集約されます。
広報担当は、投稿の目的を「告知(知らせる)」「理解促進(伝わる)」「行動促進(動いてもらう)」の段階に分け、段階ごとに反応の取り方を設計します。
たとえば告知段階では到達(リーチ)と既読性を重視し、理解促進では図解・短尺動画・Q&Aスレッドを組み合わせ、行動促進では申込導線や問い合わせ導線を明確化します。
加えて、取得した反応を庁内で共有・意思決定に接続する“受け皿”(対応フロー、FAQ、担当配分)を整えることで、単発の発信を「信頼の蓄積」へと昇華できます。
国内のSNS普及状況と示唆(高い利用率を前提にした設計)
広報設計の観点では、普及率の高さを単純な掲載拡大の根拠にするのではなく、
ターゲット別の接触習慣と接触シーン(通勤時間帯、家事の合間、夜間の余暇など)を前提に、媒体ごとの役割分担を決めることが重要です。たとえば、緊急・防災は即時性と到達性を重視して短文+画像で速報、生活情報はカルーセル画像や短尺動画で分かりやすく、地域の魅力発信は高品質ビジュアルと物語性で深い理解を促す、といった具合に「誰に・何を・どう見せるか」を設計します。
普及状況を根拠にしつつも、住民の実際の利用実態(反応率・閲覧時間・コメント傾向)を継続的に観測し、媒体配分とフォーマットを調整する運用が不可欠です。
参加型運用が生む信頼の循環(可視化・対話・改善のループ)
まず、市民の声を受け取る窓口(コメント、DM、フォーム、投票)と対応方針(返答SLA、返信の優先順位、公開・非公開の切り分け)を可視化します。
次に、受け取った意見を「庁内で誰が・いつ・どう判断するか」を決め、反映可否を分かりやすくフィードバックします。
最後に、反映結果を投稿や固定スレッドで明示し、改善の痕跡を蓄積することで、住民は「意見が届く・変わる」体験を繰り返し、信頼が強化されます。
この循環を支えるKPIは、到達(リーチ)や反応(エンゲージメント)だけでなく、反映率(受理→施策反映/改善告知までの割合)や回答SLA遵守率、再質問率の低減といった品質指標も併用します。
数値と運用手順を紐づけることで、「聞くだけで終わらない参加型」を実装できます。
自治体と企業のSNS活用の違い
自治体は「公共性・公平性・生活密着性」が軸となり、情報の正確さや住民への迅速な伝達が重視されます。
一方で企業は「顧客獲得・ブランド強化・収益性」が中心となり、訴求力やマーケティング効果が優先されます。
両者は目指す成果が異なるものの、いずれも「信頼の獲得」を前提に運用を設計する点は共通しています。
自治体アカウントの目的とKPI(安全・生活情報/参加促進)
①防災・防犯・緊急情報の迅速な伝達、
②生活に役立つ行政サービスやイベント情報の提供、
③市民参加を促す取り組みの告知と共有、
の3つに大別できます。
KPI(重要業績評価指標)は「到達率(リーチ)」「既読率」「反応数」など、情報が正しく伝わり、必要な行動につながったかどうかを測定する指標が中心となります。とくに安全情報では「拡散スピード」や「到達範囲」、生活情報では「アクセス数」や「問い合わせ件数」、参加促進では「イベント申込数」など具体的な数値を設計します。
企業アカウントの目的とKPI(認知・好意・購買行動)
①商品やサービスの認知向上、
②ブランドへの好意形成、
③購買や資料請求、問い合わせなど具体的な行動の促進、に整理されます。
KPIは「エンゲージメント率(いいね・コメント・シェアなど)」「コンバージョン率(CVR)」「広告投資対効果(ROAS/ROI)」など、直接的な成果を重視します。SNS広告と組み合わせて運用されるケースが多く、ターゲット層に合わせた精緻なセグメント設計やクリエイティブ最適化が不可欠です
共通する「信頼」設計と異なる成果指標の扱い
成果指標の扱いは異なり、自治体は「どれだけ多くの市民に届き、役立ったか」に重点を置き、企業は「どれだけ売上や顧客につながったか」を重視します。
つまり、同じSNSでも「公共コミュニケーション」と「マーケティング活動」という異なる位置付けで活用されるため、担当者は目的に応じてKPIやコンテンツの設計を根本的に変える必要があります。
成功に必要な基本ステップ(目的→媒体→コンテンツ→対話→改善)
多くの自治体や企業で失敗する要因は、この流れを途中で省略したり、短期的な発信に偏ってしまう点にあります。
段階ごとに整理し、KPI(重要業績評価指標)を設定することで、継続的に成果を積み上げることが可能になります。
運用目的の明確化(情報提供/対話促進/地域ブランド)
①市民や顧客への情報提供、
②コメントやメッセージを通じた対話促進、
③地域や企業ブランドの強化、
の3つです。
目的が曖昧なままでは、発信が単発の広報で終わり、成果の評価もできません。
たとえば「市民への生活情報を効率的に届ける」なら到達率(リーチ)がKPIになりますし、「地域イベントへの参加者を増やす」なら申込数や来場数が評価指標となります。
情報発信の目標設定(SMARTと測定設計)
よく用いられるのが
SMARTの法則Specific:具体的
Measurable:測定可能
Achievable:達成可能
Relevant:関連性
Time-bound:期限付き
です。
例えば「半年以内にSNSを通じてイベント申込を前年比20%増加させる」といった形で定義すると、担当者や関係者が成果を共有しやすくなります。
測定の仕組みとしては、アクセス解析(Googleアナリティクス、SNSインサイト)、短縮URLによるクリック計測、フォーム入力数のトラッキングなどが基本となります。
地域住民とのコミュニケーション強化(設計と運用動線)
①コメントやDMに対応する担当者とフローを決める、
②アンケートや投票機能を活用して声を可視化する、
③反映結果を再度発信して「意見が届いた」ことを示す、といった動線設計が必要です。
このプロセスが欠けると、フォロワー数が増えても実質的な信頼や満足度の向上にはつながりません。
観光・移住促進に効く計画づくり(ターゲット別メッセージ)
観光客には「アクセス・イベント・食・宿泊」を中心にした短期的な魅力を発信し、移住検討層には「生活環境・教育・医療・働く場」といった長期的な安心感を伝える必要があります。
SNS単体での発信にとどまらず、Webサイトやパンフレットへの導線設計を組み合わせることで、行動につながる確率が高まります。
LINE公式アカウントの活用(配信・対話・セグメント)
LINEは国内利用率が非常に高く、住民との直接的な接点として活用度が増しています。とくに以下の点で強みを持ちます。
1.一斉配信:行政情報やイベント情報をタイムリーに通知可能。
2.双方向対話:チャット形式で問い合わせ対応やFAQを展開できる。
3.セグメント配信:属性や行動履歴に応じた情報を出し分けできるため、効率的な情報提供が可能。
例えば、子育て世帯向けには「保育園・子育てイベント情報」、高齢者向けには「健康・介護関連情報」を配信するといった使い分けができます。
自治体にとっては「生活に密着した必ず届く情報チャネル」としての役割が大きい媒体です。
YouTube×ブログ連携で深度と到達を両立
観光PR動画や行政サービスの解説動画を配信することで、市民や観光客に分かりやすく情報を届けられます。
さらにブログや公式サイトと連携し、動画を記事に埋め込むことで検索流入(SEO)にもつなげられます。
たとえば、「移住者インタビュー動画」をYouTubeにアップロードし、ブログ記事で詳細なテキスト情報を補足することで、映像と文章の両面から信頼性と情報量を高められます。
れにより、SNS単独では得にくい「深い理解」と「検索経由の到達」を同時に実現できます。
PDCAで磨く運用最適化
初期段階では感覚的な運用に頼りがちですが、PDCAを組み込むことで、成果の蓄積やリスク回避が可能になります。ここでは3つの観点から最適化の方法を整理します。
投稿内容の分析と改善(指標・ツール・A/Bテスト)
これらは各SNSの管理画面や「SNSインサイト」で確認可能です。
さらに改善を加速させるには、
A/Bテスト(異なる画像や文言を比較して反応を測定する手法)が有効です。例えば、同じ内容を「写真付き投稿」と「短尺動画投稿」で比較すれば、どちらが住民や顧客に届きやすいかを定量的に把握できます。
市民の声の収集(コメント/投票/フォームの運用)
コメント欄やDMで届く意見に加え、投票機能やアンケートフォームを活用することで、より体系的なデータを収集できます。
特に自治体の場合は「地域課題の把握」や「施策へのフィードバック」、企業の場合は「商品改善」や「顧客満足度向上」に直結します。
重要なのは、収集した意見を庁内や社内で共有し、
意見を集めるだけで終わらず、反映の有無を公表することで信頼性も高まります。
成果指標(KPI)の設定と見直し
開始時に設定したKPI(例:フォロワー増加数、イベント参加申込数、CVR=コンバージョン率)が、運用の目的とズレていないかを確認します。
たとえば、フォロワー数だけを追いかけても、住民の満足度や参加率が向上しなければ意味がありません。
KPIは
「量(どれだけ届いたか)」
「質(どのような反応が得られたか)」
「成果(行動につながったか)」
の3階層で設計し、段階的に更新していくことが望まれます。
市民参加型を進める具体策
ここでは、実務で取り入れやすい3つの具体策を解説します。
双方向コミュニケーション設計(返信方針・可視化ルール)
たとえば、
①返信が必要なコメントと不要なコメントの分類、
②対応にかける時間の目安、
③担当部署へのエスカレーションフローを明文化しておくと、対応のブレを防げます。
また、住民の声を可視化する仕組みとして「Q&Aまとめ投稿」や「よくある質問の固定スレッド」を設けると、後から閲覧する市民にも価値が伝わりやすくなります。
コメント活用とガバナンス(分類・対応・反映プロセス)
そのため、
①コメントを「意見・要望」「質問」「クレーム・批判」に分類し、
②対応方針を決めて素早く返答、
③反映可能なものは施策や広報に組み込む、
といったプロセスが必要です。
また、批判的な意見に対しては削除ではなく「事実確認の上で丁寧に回答」することが信頼性につながります。
対応履歴を記録し、庁内や社内で共有することもガバナンスの観点で有効です。
「住民と共に発信」する仕組み(UGC促進・共同企画)
UGC(User Generated Content=ユーザーが作るコンテンツ)を活用し、ハッシュタグキャンペーンや写真コンテストを行うことで、市民が自発的に地域の魅力を発信できます。
さらに、地域イベントをSNSで共同企画したり、動画や記事に住民を登場させることで「共創型の広報」が実現します。
こうした取り組みは、単なる情報提供を超えて「一緒にまちをつくる」という意識を醸成します。
インフルエンサー/地域キャラクターの活用
住民から親しみを持たれやすく、拡散力や話題性を得られるため、SNS運用における強力な戦力となります。
地域インフルエンサーとの協力体制
観光スポット紹介や地域イベントの告知をインフルエンサーと共同で発信することで、公式アカウントだけでは届きにくい層へ自然にアプローチできます。
連携を成功させるためには、
①ターゲット層を明確にする、
②価値観や発信内容が自治体の方針と合致する人物を選ぶ、
③成果を数値化し効果測定を行う、
といった手順が欠かせません。
また、事前に契約や役割分担を明確にし、長期的な関係性を築くことが持続可能な運用につながります。
マスコットキャラクターを活かした広報戦略
キャラクターを中心としたストーリー投稿やイベント告知は、SNS上で拡散されやすく、住民の愛着を高めます。
実際の事例では、群馬県前橋市の「ころとん」や熊本県の「くまモン」が代表例です。
イベント連動の投稿やコラボキャンペーンを行い、市民と観光客の双方から支持を獲得しています。
自治体が独自キャラクターを持たない場合でも、既存の観光キャラや企業とのコラボで代替可能です。
SNS投稿で魅力を最大化する工夫
インフルエンサーやキャラクターを活用した投稿では、以下の工夫が効果的です。
一貫性あるビジュアル:デザインや色調を統一し、公式アカウントの世界観を構築。
参加型企画:ハッシュタグキャンペーンやフォロワー投票で住民を巻き込み、共創意識を醸成。
ストーリーテリング:地域の歴史や文化を物語として発信し、共感を呼ぶ。
定期的な露出:不定期の起用ではなく、計画的に登場させることで認知を定着させる。
これらを組み合わせることで、インフルエンサーやキャラクターを単なる広告塔ではなく「地域と市民をつなぐシンボル」として活用できます。
LINE公式アカウントの高度活用
緊急情報の迅速配信(事前準備・テンプレート・検証)
そのためには、あらかじめ配信テンプレートを用意し、担当者がすぐに投稿できる体制を整えることが不可欠です。
例えば「地震発生」「避難所開設」「交通規制」など、よくあるケースを定型文で準備しておくことで、混乱時でも確実に配信できます。
また、訓練やテスト配信を定期的に行い、想定外の状況でも機能するか検証することが求められます。
拡張ツールの導入で強化(自動応答・セグメント・アンケート)
LINE公式アカウントは、標準機能だけでなく外部ツールを組み合わせることで飛躍的に活用の幅が広がります。代表的な機能は以下の通りです。
・自動応答(チャットボット):よくある質問に即時回答し、担当者の負担を軽減。
・セグメント配信:年齢・地域・興味関心に応じた情報を出し分け。
・アンケート機能:施策やサービス改善のために意見を収集。
これらを適切に導入すれば、「誰に・どんな情報を・どのタイミングで」届けるかを高度に設計できます。
セグメント配信とアンケート活用の実装例
また、アンケート機能を活用すれば、施策やイベントの満足度を測定し、今後の改善に活かせます。
配信→反応収集→改善のサイクルをLINE単体で完結できる点は、大きな強みといえます。
成功事例に学ぶ(自治体)
ここで代表的な成功例を紹介し、運用に生かせるポイントを整理します。
自治体の成功パターン(ビジュアル・ハッシュタグ・対話)
横浜市(Instagram活用):
観光誘客を目的に公式アカウント「@findyouryokohama_japan」を運用。継続的な投稿によりフォロワー数は10万人を突破し、国内自治体の中でも先進的な事例となっています。
葉山町(神奈川県):
自然や暮らしの風景を伝えるInstagram投稿を継続し、「#葉山歩き」など独自ハッシュタグを展開。短期間で町の人口を超えるフォロワーを獲得し、移住促進にも寄与しました。
Xのハッシュタグ戦略の勘所(設計・運用・検証)
Facebookでのタイムリー運用(告知→報告→対話設計)
前橋市:
では、公式アカウントを通じてイベント情報を「事前告知→当日レポート→事後アンケート」という流れで発信。情報が単なる告知に終わらず、参加者の声を拾って次回改善に活かす「循環型の発信」を確立しました。
課題と対策(炎上・公平性・ネガティブ対応・透明性)
炎上リスクの未然防止と初期対応
表現や写真に差別的・誤解を招く要素がないかを複数人で確認する「ダブルチェック」を運用ルール化しましょう。
また、投稿内容だけでなく、コメント欄での反応にも注意が必要です。万一炎上が発生した場合は、
①事実確認を迅速に行い、
②誤りがあれば速やかに修正・謝罪、
③不適切な投稿は削除・非表示を検討、
というフローをあらかじめ定めておくと対応がぶれません。
ガイドライン整備と公平性の担保
特定の団体や個人を優遇しているように見える発信は避け、情報提供の基準をガイドラインとして明文化しましょう。
たとえば「イベント紹介は公共性のあるものに限定」「広告やPRはタイアップ明記」といったルールを設定し、職員や担当者全員が共有することが信頼維持につながります。
ネガティブコメント対応の原則
これを無視したり削除するだけでは不信感を招きます。
基本方針は、
①事実関係を確認したうえで冷静に対応する、
②感情的な応酬は避け、丁寧かつ簡潔な回答を心がける、
③根拠のない誹謗中傷は非表示・通報で対応する、
の3点です。
否定的な声にも耳を傾け、改善につなげる姿勢を示すことが「参加型SNS」の信頼基盤になります。
情報公開と説明責任(透明性の運用)
特に自治体の場合、情報が偏ったり一部だけ公開されると不信感を招きます。
そこで、
①発信の根拠や背景を簡潔に示す、
②誤解を避けるためのリンク先(公式サイトや資料)を添える、
③改善や方針変更の経緯を投稿で公表する、
といった取り組みが有効です。
透明性を確保することで、住民からの信頼は長期的に積み重なります。
体制づくり(負担軽減とスキル格差の解消)
持続的に成果を出すためには、ツールの導入や人材育成、外部リソースとの連携によって「分散型の体制」を構築することが重要です。
業務効率化ツールの導入手順と評価軸
代表的な機能は「予約投稿」「エンゲージメント分析」「レポート自動作成」などです。
導入時は、
①使いやすさ、
②費用対効果、
③セキュリティ、
④サポート体制、
を評価軸に比較すると選定ミスを防げます。
自治体の場合は入札・予算承認プロセスが必要になるため、事前に費用と導入目的を明確化しておくとスムーズです。
SNS人材の育成プログラム(研修/実践/評価)
①初級研修(基礎用語・媒体特性・リスク管理)、
②実践研修(投稿企画・効果測定・トラブル対応)、
③評価とフィードバック(成果指標に基づく改善)
の3段階で設計するのが望ましい方法です。
さらに、担当者同士で成功事例や失敗事例を共有する「ナレッジ共有会」を定期的に実施すると、現場の知見を蓄積できます。
外部専門家との連携モデル(役割分担と成果管理)
依頼する場合は、
①クリエイティブ制作(写真・動画)、
②分析・レポーティング、
③戦略設計やアドバイス、
など役割を明確に分担します。
また、成果管理の観点からは「月次レポートの提出」「KPI達成度の検証」「改善提案の有無」を評価基準として契約に盛り込むと、外部リソースを効果的に活用できます。
未来展望と新しい情報交流
特にAIやデジタル技術の進化により、今後のSNSは「情報発信」だけでなく「参加と共創のプラットフォーム」としての役割を強めていくと考えられます。
地域ファンづくりの継続施策(イベント×SNS)
例えば、祭りや観光イベントをライブ配信し、ハッシュタグ投稿を住民や来訪者に促すことで拡散効果が高まります。
終了後もフォトコンテストや参加者アンケートをSNSで展開すれば、関心を継続的につなぎとめられます。
観光・移住につながる情報設計(ターゲット別導線)
観光客向けには「食・宿泊・アクセス」の短期的魅力を、移住希望者向けには「教育・医療・雇用・暮らし」といった長期的な安心感を発信します。
さらに、SNS投稿から公式サイトやパンフレットへの導線を設計し、最終的に問い合わせや行動につなげる流れを整備することが重要です。
地域ブランド×SNSの相乗効果
例えば「特産品レシピ投稿キャンペーン」を展開すれば、消費者自身が地域ブランドの価値を拡散してくれます。
AIによる住民サービスと運用高度化
AIの導入により、SNS運用はさらに効率的かつ効果的になります。
・チャットボットによる問い合わせ対応:ごみ収集日、手続き案内、災害情報などを自動応答し、担当者の負担を軽減。
・自然言語処理による投稿作成補助:AIが文章やキャッチコピーを提案し、担当者は最終チェックに集中できる。
・画像生成AIによるビジュアル作成:観光PRやイベント告知で、独自の画像を短時間で用意可能。
・感情分析・トレンド分析:市民のコメントをAIが分析し、肯定的/否定的傾向を可視化して改善に活かす。
これにより、少人数でも高度なSNS運用を実現でき、住民サービスの質を落とさずに効率を高められます。
行政×市民協働の加速(参加設計と成果可視化)
特にAI分析と組み合わせることで、数千件に及ぶ意見を短時間で集計・可視化し、迅速な意思決定に反映できる点が強みです。
デジタル技術の進化と広報の更新
これらの技術を適切に取り入れることで、住民や観光客にとってより分かりやすく、魅力的な情報提供が可能になります。
WEB広告運用ならWEBTANOMOOO(ウエブタノモー)

もし広告代理店への依頼を検討されているなら、ぜひ私たちWEBタノモーにお任せください。
WEBタノモーではリスティング広告を中心に、SNS広告やYouTube広告などの運用代行を承っております。
・クライアント様のアカウントで運用推奨(透明性の高い運用)
・広告費が多くなるほどお得なプラン
・URLで一括管理のオンラインレポート
このように、初めてのWEB広告運用でも安心して初めていただけるような環境を整えております。
ニーズに沿ったラLPやHPの制作・動画制作、バナー制作もおこなっていますので、とにかく任せたい方はぜひお気軽にご相談ください。